
404 ERROR 404 ERROR
申し訳ありませんが、現在このページは存在しません。
以下ページにアクセスして目的のページを再度お探しくださいませ。
※5秒後に自動的にページが切り替わります。
〒653-0013
神戸市長田区一番町2丁目4番地
 地図で見る Tel: 078-576-5251
地図で見る Tel: 078-576-5251
Fax:078-576-5358(代表)/ 078-579-1943(病診連携室 ※診療情報提供書送付先)
 地図で見る
地図で見る
-
病院案内
- 院長あいさつ
- 病院概要 基本理念・方針・沿革
- 患者の権利と責務、医の倫理
- フロアマップ、快適な環境づくりについて
- 包括同意について
- 医療安全の取り組み
- 交通アクセス
- 当院の特長(取り組み)
- 病院情報の公表
- 臨床データの研究利用に関するお願い
- ご寄付のお願い
- 一般社団法人National Clinical Database (NCD)の 事業への参加について
- 臨床評価指標
- 適切な意思決定に関する指針
- 医療費後払いサービス
- 院内フリーWi-Fi
- 厚生労働大臣が定める掲載事項
-
当院のがん診療について
-
外来のご案内
- 初めて受診される方へ
- 診療の流れ
- 診察週間予定表
- 救急診療のご案内
- 検査のご案内
- セカンドオピニオン外来のご案内
- 患者サービス向上の取り組み
- 予約制・紹介制のご案内
- 診断書・証明書について
- 治験・臨床試験について
- 病理解剖(剖検)についてのお願い
- 宗教的理由等による輸血拒否に関する当院の方針
- かかりつけ医について
-
入院のご案内
-
診療科・部門のご案内
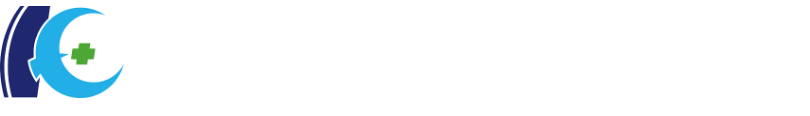




 救命救急外来の受付は24時間行っています。
救命救急外来の受付は24時間行っています。
