
患者の権利と責務、
医の倫理 RIGHTS AND RESPONSIBILITIES, ETHICS
患者の権利と責務
医師ならびに医療機関と患者や社会との関係は、近年著しく変化してきましたが、医療者(医師、看護師、コメディカルスタッフなど)は、常に自らの良心に従い、患者の最善の利益のために行動すべきであることに変わりありません。当院では、世界医師会「患者の権利に関するリスボン宣言」の精神のもと、「患者の権利章典」を制定し、患者の人権を尊重した「患者中心のチーム医療」を推進します。
一方、患者の権利を尊重した「患者中心のチーム医療」をすすめる中では、患者自身の主体的なかかわりが不可欠かつ重要であり、患者・家族の皆さんにも「患者中心のチーム医療」を進める大切な役割を自覚していただく必要があります。また、病院も社会の一部であり、患者の権利だけが無秩序に守られるわけではなく、患者自身が守るべきルールもあります。
以下に掲げる事項は、患者が医療を受けるにあたって、守られるべき権利と患者自身に求められる責務とも言える内容であり、十分に理解していただきますようにお願いいたします。
患者の権利
良質かつ適切な医療を公正に受ける権利をもっています。
患者さんはだれでも、どんな病気であっても、社会的な地位、国籍、宗教などにより差別されることなく、適切な医学水準に基づいた安全かつ効果的な医療を受ける権利をもっています。
医師・病院を自由に選択し、他の医師の意見を求める権利をもっています。
患者さんは、どのような検査や治療を受ける上においても、担当の医師、病院を自由に選択する権利を持っています。また、どのような診療の段階においても、他の医師の意見(セカンド・オピニオン)を求める権利をもっています。
十分な説明と情報提供を受けた上で、治療方法などを自らの意思で選択する権利をもっています。
患者さんは、自分自身に関わる診療行為に関して、それを受けるかどうかを自由に決定する権利をもっています。また、その意思決定を行う上で必要となる医療情報を得る権利をもっています。
人格や価値観が尊重され、人としての尊厳が守られる権利をもっています。
患者さんは、いかなる状態にあっても、一人の人間として、その人格や価値観を尊重され、尊厳が保たれる権利をもっています。また、プライバシーが守られる権利をもっています。
意識がないか判断能力を欠く場合や未成年者の場合、代行者に決定を委ねる権利をもっています。
患者さんが意識不明か、その他の理由で意思を表明できない場合や未成年の場合には、法律上の権限を有する代理人が患者さんの代わりに意思決定をする権利をもっています。
自分の診療記録の情報を受ける権利をもっています。
患者さんは、自分の診療記録の開示を含め、自分の診療情報に関して十分な説明を受ける権利をもっています。逆に、知りたくない情報を知らされない権利ももっています。
個人情報の秘密が守られる権利をもっています。
患者さんは、診療の過程で得られた自分の個人情報の秘密が守られる権利をもっています。
健康教育を受ける権利をもっています。
すべての人は、個人の健康に対する自己責任をもつと同時に、疾病の予防および早期発見についての手法や保健サービスの利用などを含めた健康教育を受ける権利をもっています。
子どもの権利 (当院は小児科学会の「医療における子ども憲章」に準拠します)
①人として大切にされ、自分らしく生きる権利
あなたは病気や障がい、年齢に関係なく人として大切にされ、あなたらしく生きる権利を持っています。
②子どもにとって一番よいこと(子どもの最善の利益)を考えてもらう権利
あなたは、医療の場であなたに関係することが決められるとき、すべてにおいて、周囲のおとなにそれが「あなたにとってもっとも良いことか」を第一に考えてもらえる権利を持っています。
③安心・安全な環境で生活する権利
あなたはいつでも自分らしく健やかでいられるように、安心、安全な環境で生活できるよう支えられる権利を持っています。もしあなたが病気になったときには、安心、あなたが病気になったときには、安心・安全な場で、できるだけ不安のないようなやり方で医療ケア(こころやからだの健康のために必要なお世話)を受けられます。
④病院などでお親や大切な人といっしょにいる権利
あなたは、医療を受けるとき、お父さん、お母さん、またはそれに代わる人とできる限りいっしょにいることができます。
⑤必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利
あなたは、自分の健康を守るためにすべての情報について、あなたにわかりやすい方法で、説明をうける権利を持っています。そして、あなた自身の方法で、自分の意思や意見を伝える権利を持っていて、できるだけその気持ち・希望・意見の通りにできるように努力してもらえます。
⑥希望どおりにならなかったときに理由を説明してもらう権利
あなたの気持ち・希望・意見の通りにすることができない場合は、なぜそうなったのか、その理由などについてわかりやすい説明を受けたり、その理由が納得できないときは、さらにあなたの意見を伝えたりする機会があります。
⑦差別されず、こころやからだを傷つけられない権利
あなたは、病気や障害、その他あらゆる面において差別されることなく、あなたのこころやからだを傷つけるあらゆる行為から守られます。
⑧自分のことを勝手にだれかに言われない権利
あなたのからだや病気のことは、あなたにとって大切な情報であり、あなたのものです。あなたらしく生活をすることに守るために、あなたのからだや病気、障害に関することが他のひとに伝わらないように守られます。また、だれかがあなたのからだや病気、障害のことを他のひとに伝える必要があるときには、その理由とともに伝えてもよいかをあなたに確認をします。
⑨病気のときも遊んだり勉強したりする権利
あなたは、病気や障害の有無に関わらず、そして入院中や災害などを含むどんなときも、年齢や症状などにあって遊ぶ権利と学ぶ権利を持っていて、あなたらしく生活することができます。
⑩訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利
あなたは、必要な訓練を受け、技術を身につけたスタッフによって医療やケア(気配り、世話など)を受ける権利を持っています。
⑪今だけでなく将来も続けて医療やケアを受ける権利
あなたは継続的な医療やケア(気配り、世話など)を受けることができます。また、日々の生活の中でさまざまな立場のおとなに支えてもらう権利を持っています。
患者の責務
医療が安全かつ適切に行われるために、患者自身が医療者とともにチーム医療に主体的にかかわることが必要です。
患者自身の主体的なチーム医療への参加は、患者さんのもつ権利であるとともに、責務でもあることをご理解ください。
- 患者さんが医療に期待し求めることと医療者の考える適切な医療がうまくかみ合わなければ、患者さんのための医療は成り立ちません。
- 当院では、診療における様々な局面に、患者さんへの説明や意思の確認などを行うよう努めていますが、その際には遠慮なくご自身の意思や意見、疑問を担当者に伝えてください。
医療者の説明に対しては、十分に納得できるまでお尋ねください。
- 検査や治療によっては苦痛を伴うものもありますし、多くの治療が患者さんの協力なしには実施、継続することができません。そのため、患者さん自身が病気のことや診断・治療の必要性などについて十分理解していただくことが必要です。
- どうしても納得できない場合には、他の病院・他の医師の意見(セカンド・オピニオン)を求めることをお勧めします。
医療者が診療において的確な判断を行っていくため、病状や家族歴、既往歴、アレルギーの有無、薬の服用状況などの情報は、できる限り正確にお知らせください。
- 検査や手術、処置などの治療を安全に受けるために、今までに治療を受けたことのある病気や服用中の薬品名、アレルギーなどの副作用の経験などを担当者にお知らせください。
- 化学療法(抗がん剤治療)などの薬物療法を受けているときには、副作用の症状などを必ず担当者にお伝えください。
- 緩和医療を受けるときには、痛みなどの苦痛の程度を遠慮なくお知らせください。また、ご自身の死生観や治療方針に関するご意思を担当者にお話しください。
医療の安全確保のための取り組みにも患者さんの協力が必要です。
自分自身が受ける医療行為、投与される薬などに関する疑問や不安は、遠慮なく医師や医療スタッフにお伝えください。
- 「医療事故を防ぐために、患者さんにできる最も重要なことは、患者さん自身が医療チームの一員として積極的に参加することです」と米国保健省の下部組織のAHRQ(医療の質研究疔)が公開している「医療事故を予防する20の秘訣」(http://www.ahrq.gov/consumer/20tips.htm)のトップに掲げられています。
- 医療者によるチェックやシステムの欠陥等をすり抜けてきたエラーを事故になる直前に防ぐための「安全装置」としての力を患者さん自身がもっているのです。
患者間違いによる事故を防ぐための取り組みへの協力をお願いします。
- 思い込みから生じるひと間違いを防ぐために、当院では、診察や検査の前、薬の服用や注射の前に、患者さんのフルネームを確認する取り組みを推進していますので、ご協力をお願いします。
入院中の転倒・転落事故を防ぐための取り組みへの協力をお願いします。
- 入院中は、転倒や転落事故を防ぐための医療者の指示に従ってください。患者さんの状況によっては、家族の方々に付き添いを依頼することがありますので、ご協力をお願いします。
- 入院中、患者さんの安全確保のために、やむを得ず患者さんの行動を制限することがあります。その際には担当者より説明をしますので、ご協力お願いします。
静脈血栓塞栓症を防ぐための取り組みへの協力をお願いします。
- 入院パンフレット「肺血栓塞栓症の予防のために」をお読みください。入院中は、肺塞栓症防止のために必要な予防策を行うことがありますので、ご協力お願いします。
検査や治療が安全に実施できるように、医療者の指示は必ずお守りください。
- 当院では、検査や治療に伴う患者さんの苦痛を軽減し、医療の安全性を高めるための様々な努力を行っていますが、患者さんの協力がなければ安全性の確保は容易ではありません。医療の安全を確保するための医療者の指示に従ってください。
院内感染の防止のための取り組みにも患者さんの協力が必要です。
咳エチケットについて
- インフルエンザなどの感染症の蔓延を防ぐため、咳やくしゃみをするときは、口と鼻をティッシュで覆ってください。そして手を洗ってください。咳やくしゃみをされている場合、マスクをしていただくようお願いする場合があります。
お見舞いについて
- かぜ症状や下痢、嘔吐などの症状がある場合は、お見舞いをご遠慮ください。抵抗力のない小さなお子さんの面会もなるべく控えてください。
感染予防対策への協力について
- 患者さんの状況によりましては、職員より手洗いやマスク・ガウンの使用などを個別にお願いする場合があります。わからないことは何でも職員にお尋ねください。
以下のような犯罪行為、迷惑行為、その他これらに準じる行為を禁止いたします。これらの行為により、当院との信頼関係が破たんした場合は、当院での診療を原則としてお断りいたします。
- 暴言・暴力行為・脅迫・窃盗
- 危険物の持ち込み・飲酒
- 入院時における無断外出・外泊
- 他の患者もしくは医療従事者への迷惑行為
- セクシャル・ハラスメント
暴力行為やセクシャル・ハラスメントは犯罪です。
- 暴力・暴言などで他の患者さんにご迷惑がかかる場合や医療者の診療行為が妨げられる場合には、患者さんと言えども当院での診察を中止することがあります。また、必要に応じて警察へ通報することがあります。
その他、病院内の規則をお守りください。
病院は、多くの患者さんが集まり、医療を受ける場です。すべての患者さんが快適な環境で医療を受けられるように協力をお願いします。
当院は敷地内禁煙です。
- 喫煙はご自身だけでなく、周りの人々の健康に悪影響を与えます。病院内では必ず禁煙をお守りください。
(平成24年7月10日改訂)
当院は、臨床研修病院(医師免許取得後2年間の医師:研修医を実践教育する病院)の指定を受けています。研修医が担当医として主治医の責任指導の下に診療・治療などを行う事があります。また、医師など病院職員が、患者のプライバシーを確実に遵守して、治療上の成績などを学会に発表する事があります。これらの点につきご了承いただきたく存じます。
当院は、急性期の患者に対する高度医療、救急医療に重点を置いています。急性期の入院治療を必要とする患者が、すぐに入院できる体制を整える事に最大限の努力をしております。
そのため、患者の急性期の病状が安定し入院治療が必要でなくなった段階で、当院の外来又はご紹介をいただいた医療機関やご自宅近くの医療機関へ診療を引き継ぎますので、ご協力をお願いいたします。
なお、他の医療機関へ紹介する場合は、患者にとって最善の医療が受けられるよう、病状、検査、治療の経過などを添えてご紹介させていただきます。
医の倫理
当院では、医の倫理にかかわる諸問題に対して、患者の人権を守ることを第一と考え、病院の理念と基本方針、患者の権利章典、医療者の倫理綱領、患者の権利に関する基本方針などの指針を示し、すべての職員への周知・教育を行っています。
医の倫理
医療者の倫理綱領
当院では、医の倫理にかかわる諸問題に対して、患者の人権を守ることを第一と考え、病院の理念と基本方針、患者の権利章典、医療者の倫理綱領、患者の権利に関する基本方針などの指針を示し、すべての職員への周知・教育を行っています。
医学および医療は、病める人の治療はもとより、人びとの健康の維持もしくは増進を図るもので、医療者(医師、看護師、コメディカルスタッフなど)は責任の重大性を認識し、すべての人に奉仕するものである。
- 医療者は生涯学習の精神を保ち、つねに医学の知識と技術の習得に努めるとともに、その進歩・発展に尽くす。
- 医療者はこの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるように心掛ける。
- 医療者は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得るように努める。
- 医療者は互いに尊敬し、協力して医療に尽くす。
- 医療者は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、法規範の遵守および法秩序の形成に努める。
- 医療者は医業にあたって営利を目的としない。
(平成20年12月8日制定)
治験や臨床研究における倫理
医学研究における倫理の問題、新薬の治験や遺伝子治療等新しい治療技術の開発に関わる臨床研究に関しては、外部委員を含めた倫理委員会、治験審査委員会で審議を行い、常に患者の人権と医の倫理に配慮しています。また、一般的な倫理研究に関しては、倫理問題検討委員会や臨床研究審査委員会において患者の権利やプライバシーの保護、個人情報の保護の観点から審議を行っています。
臨床における倫理
悪性疾患の病名告知や予後の告知に関しては、患者の知る権利と知らないでいる権利の問題、家族への告知を希望されない場合の対応の問題などで、簡単に答えを出すことのできないケースがあり、個々の患者さんに応じた検討が求められます。終末期における治療の差し控えの問題や延命処置としての心肺蘇生法の実施や人工呼吸器の装着など治療法の選択の問題なども、患者の意思の尊重や人としての尊厳を守る面などから、倫理的な検討を要する問題であります。
当院では、このような臨床における倫理に関わる問題について、主治医が単独で判断せず、複数の医師や看護師、ソーシャルワーカーを含めた医療チームとともに、患者さん自身や家族の方々を含めた話し合いを行い、治療方針を決定するように努めています。さらに、臨床の現場で結論を出せないような倫理に関わる問題については、倫理問題検討委員会で、常に患者さんの意思と権利を第一に考慮した最善の方法を検討します。
その他、医療安全管理委員会、患者サービス向上委員会など各種委員会での審議や、臨床の現場での事例検討会において、臨床における倫理の諸問題について検討を行い、患者さんの人権を尊重した対応を選択し決定しています。
臓器移植に関わる倫理
『臓器の移植に関する法律』に規定されている臓器のうち腎臓、膵臓、眼球(角膜)については心臓が停止した死後においても臓器の提供・移植は可能です。脳死下での臓器提供のように提供施設の指定はありませんが、実際の腎臓、膵臓の提供においては心停止前からの準備が必要です。当院では『臓器の移植に関する法律』に則り、『臓器提供に関するマニュアル』に準じて、心臓が停止した死後の腎臓などの臓器摘出に対応しています。
当院では、患者さん自身や家族の方々の臓器提供の意思を尊重するとともに、家族の方々の心情にも配慮して対応するよう努めています。具体的には、患者さんが昏睡状態で終末期にあると判断され、家族の方々がそれを受容された場合、その後の治療方針は家族の方々と担当医師・チームの話し合いで決定されます。その中で、患者さんや家族の方々の臓器提供の意思が示された場合に、担当医・チームは臓器提供者の適応を検討します。そして、患者さんがその基準を満たす場合には、家族の方々に移植コーディネーターの説明を聞くか否かの確認を行います。その後、担当医・チームは移植コーディネーターと密接に情報交換を行い、患者さん自身や家族の方々の臓器提供の意思が生かされるように努力します。
臓器提供の意思をお持ちの患者さんや家族の方は、いつでもご遠慮なく担当医や看護師など医療者にご相談下さい。
患者の権利の尊重に関する基本方針
当院では、「患者の権利」に定めた患者の権利を尊重し、守るべく、以下の基本方針を職員に周知・徹底します。
- 患者に対して常に公平であるとともに、適切で安全な医療の提供や医療の質の向上のために知識・技術の習得・向上に努めます。
- 個々の患者の人格や価値観を尊重し、患者との信頼関係、パートナーシップのもとで「患者中心のチーム医療」の実践に努めます。
- 終末期にある患者に対しても、最新の医療知識に基づき苦痛を緩和し、人としての尊厳を保てるように治療、ケアを行います。
- 患者が意識不明か、その他の理由で意思を表明できない場合や未成年の場合には、法律上の権限を有する代理人に対して、十分な情報提供を行い、患者の最善の利益のための意思決定を支援します。
- 病気、検査、治療、見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で十分に説明し、診療内容についての患者の理解と意思決定を助けます。
- 患者が他院の専門医のセカンド・オピニオンを要望された場合には診療情報提供書の作成など適切に対応します。
- 患者から自分自身の診療録の開示を求められた場合には、原則的に診療録の開示を行います。
- 個人情報保護に関する取り決めを行い、患者の個人情報の機密保持に努めます。また、入院生活において、患者のプライバシーが守られるように努めます。
- 患者自身の健康増進の努力を支援するために、健康教育のための市民公開講座や療養相談、医療相談窓口の活動に積極的に取り組みます。
(平成20年12月8日制定)
〒653-0013
神戸市長田区一番町2丁目4番地
 地図で見る Tel: 078-576-5251
地図で見る Tel: 078-576-5251
Fax:078-576-5358(代表)/ 078-579-1943(病診連携室 ※診療情報提供書送付先)
 地図で見る
地図で見る
-
病院案内
- 院長あいさつ
- 病院概要 基本理念・方針・沿革
- 患者の権利と責務、医の倫理
- フロアマップ、快適な環境づくりについて
- 包括同意について
- 医療安全の取り組み
- 交通アクセス
- 当院の特長(取り組み)
- 病院情報の公表
- 臨床データの研究利用に関するお願い
- ご寄付のお願い
- 一般社団法人National Clinical Database (NCD)の 事業への参加について
- 臨床評価指標
- 適切な意思決定に関する指針
- 医療費後払いサービス
- 院内フリーWi-Fi
- 厚生労働大臣が定める掲載事項
-
当院のがん診療について
-
外来のご案内
- 初めて受診される方へ
- 診療の流れ
- 診察週間予定表
- 救急診療のご案内
- 検査のご案内
- セカンドオピニオン外来のご案内
- Web予約システムのご案内
- 患者サービス向上の取り組み
- 予約制・紹介制のご案内
- 診断書・証明書について
- 治験・臨床試験について
- 病理解剖(剖検)についてのお願い
- 宗教的理由等による輸血拒否に関する当院の方針
- かかりつけ医について
-
入院のご案内
-
診療科・部門のご案内
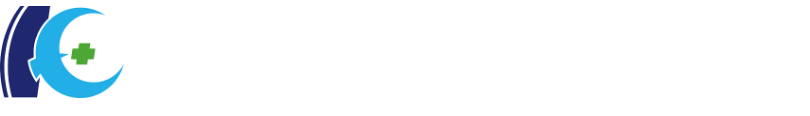




 救命救急外来の受付は24時間行っています。
救命救急外来の受付は24時間行っています。
