
医療安全の取り組み MEDICAL SAFETY
当院の基本方針と組織体制
医療の質と安全は最重要課題
医療における安全の確保は、医療を提供する者にとっての最重要課題です。
患者・家族の方々に安心して医療を受けていただけるように、当院では基本理念・基本方針に医療の安全を掲げ、個々の医療者とともに病院組織全体で医療の質の向上と安全の確保に努めています。
医療安全を推進する院内の組織体制
医療の安全を高めるために、当院では個々の職員の努力だけに頼るのではなく、医療安全管理委員会とその実働部隊としての医療安全管理室を設置し、各部署のセーフティマネージャー(医療安全現場責任者)とともに組織的な改善活動に取り組んでいます。
医療安全管理室の主な活動
医療に伴う有害事象の原因分析と安全対策の立案・実践
医療に伴って発生した有害事象(医療事故を含む)やヒヤリとした、ハッとした事象を病院職員に自主的に報告してもらい、その有害事象の原因や誘因を検討します。そして、有害事象を未然に防ぐ対策や有害事象による被害を小さくする対策などを立案し、周知の上、実行に移しています。
医療安全のための職員教育・研修活動
医療安全活動の啓発・普及のために、講演会や実技トレーニング、ワークショップ形式などの職員研修を企画し実施しています。また、個々のテーマで、職員への注意喚起や安全対策の周知のために「安全管理ニューズレター」を発行しています。
安全管理パトロールの実施
医療現場の危険箇所や場面を調査し、職員の安全活動の実践状況を確認して、現場への改善指導を行っています。
医療安全管理室のスタッフ
医療安全管理室のメンバーは、多職種で構成され、病院全体の取り組みを行っています。
| 室長 | 医師1名(医療安全担当副院長) |
|---|---|
| 副室長 | 看護師1名(医療安全管理専従)、医師1名 |
| スタッフ |
薬剤師1名、 医事課3名、総務課1名、交代制医師1名、臨床工学技師1名、 診療放射線技師1名 |
当院が取り組んでいること
確認作業の徹底のための「指差し・声だし確認」の推進
当院では産業界のノウハウに学び、指示出し・指示受け・実施の際のエラーを防ぐために、「指差し・声出し確認」の周知・徹底に努めています。

確認作業の徹底のための「タイムアウト」
手術部では、手術室入室時に看護師と麻酔科医により患者確認を行うとともに、手術体位や術野消毒の前に、一旦作業を止めて(タイムアウト)、外科系主治医・担当医と麻酔科医、看護師が患者確認だけでなく予定手術術式や左右の区別などを最終確認する取り組みを推進し、思い込みによる間違い防止に努めています。
放射線部門でも、侵襲的検査・処置を行う場合にタイムアウトを行い、主治医と看護師、診療放射線技師による患者確認、実施検査・処置確認、部位確認を実施しています。
また、透析室・外来・病棟などにおいても侵襲的な処置を行う場合には、複数の医療者で上記と同様のタイムアウトを実施し、確認作業の徹底に取り組んでいます。
「作業中断」イエローカードの活用
多忙な病棟業務においては、患者さんからのナースコールをはじめ様々な業務が重なり、作業を中断せざるをえないことがあります。
こういった場合、作業再開時に確認が疎かになったり、別の職員が作業を引き継いだ時に思い込みによる間違いをする危険性が生じます。

そこで、誰が作業を中断しているのかを明示し、職員名入りのイエローカードで、再開時の確認不足や引き継ぎミスの防止に取り組んでいます。
患者間違い防止の取り組み
ネームバンドの活用や診察券などでのフルネームの確認だけでなく、患者さん自身にも氏名を名乗っていただく方法を推進し、患者間違いの防止に努めています。
安全な医療の提供のため、ご協力をよろしくお願いします。
ダブルチェックの必要な薬剤リストの作成・改訂
毒薬、劇薬、危険薬など、使い方を間違えば身体に大きな影響を及ぼす薬がたくさんあります。これらの薬は、思い込みによる間違いを減らすためにダブルチェックが必要な薬剤としてリストにしています。薬剤部では調剤する薬剤師と監査する薬剤師によるダブルチェック、病棟などでは看護師同士や看護師と医師によるダブルチェックを行っています。
治療の標準化の取り組み
最近では、各学会で疾患別の診断・治療ガイドラインの作成が進んでいます。
当院でも、これらのガイドラインに準拠した診断や治療の実践に努めています。クリニカルパスの作成・活用、各種説明文書の作成・活用などもその一環です。
また、静脈血栓塞栓症予防や敗血症診療の質向上のための当院版ガイドラインの作成や低血糖時の共通指示、転倒・転落事故による頭部打撲時の対応手順の作成などを行っています。
医療現場における改善活動 案・do・トライ 一歩前へ!の推進
医療の質の向上や安全性の確保のためだけでなく、病院における様々な業務の改善のために、各部署やチーム、グループが行っている活動に光を当てて応援する試みを平成21年度より開始しました。
年に1回、院内の様々な職種の取り組みを紹介する改善活動発表を行い、病院全体に地道な改善活動の輪を広げる取り組みを行っています。
eラーニング(Safety Plus®)の導入
医療安全を高めるために、医療安全に関する院内研修を病院として実施し、職員全員が受講することが重要です。時間の都合で全体研修に参加できない職員のため、ネット環境があれば研修ができるeラーニング(Safety Plus®、エルゼビア・ジャパン社)を平成30年8月に導入しました。コースは現在約55のコンテンツがあり、全職員が研修を受けることができるシステムにしています。
医療安全研修会
医療安全に関する職員研修も大切な取り組みとして積極的に行っています。令和6年度に開催したものは以下の通りです。
|
4月2日 |
アナフィラキシー対応 (1年次研修医対象) |
受講者:12名 |
|---|---|---|
|
4月16,18,25日 |
輸液ポンプ研修 (新人看護師対象) |
受講者:60名 |
|
4月19日 |
与薬演習 (新人看護師対象) |
受講者:60名 |
|
5月15、17,20,22日 |
MRI安全講習会 (新人対象) |
受講者:75名 |
|
7月 |
第1回医療安全研修会 (eラーニングで開催) |
「昨年度のインシデント事例より」 |
|
9月12日 |
第2回医療安全研修会 (eラーニング+集合開催) |
「医師の働き方改革と応召義務」 受講者:286名 |
|
9月 |
第3回医療安全研修会 (eラーニングで開催) |
「放射線安全管理研修」 受講者:184名 |
|
9月 |
第4回医療安全研修会 (eラーニングで開催) (医師・看護師・薬剤師対象) |
「インスリン講習会」 受講者:415名 |
|
11月 |
第5回医療安全研修会 |
「医療ガス研修」 |
|
2月 |
第6回医療安全研修会 |
「身体拘束研修」 |
|
2月 |
第7回医療安全研修会 |
「RRS研修」 |
その他の取り組み
- 令和5年度
-
- 採血検査などによる神経障害発生時の対応指針を見直しました。
- 暴力行為等対策として、ICレコーダーによる録音指針を作成しました。
- 放射線技術部者医療安全研修対象者を改訂しました。
- 種々の対策をとったにもかかわらず、外来エスカレーターでの転倒事例が続いたため、使用禁止としました。
- MRI検査のチェックリストの内容を更新し、血糖測定器、貼り薬、カイロの追加しました。
- 荻原みさき病院、中央市民病院、神戸アイセンターと医療安全管理相互視察を行いました。
- 令和4年度
-
- 医師からのインシデント・アクシデント報告に関して、診療科別に報告内容・件数がわかるようにしました。
- 医療機器の管理体制を見直し、機器を購入する経理担当と臨床工学技士との連携を強化しました。
- 急変死亡時における死亡時画像診断(autopsy imaging; Ai) に関する案内を医師診療指針に追記し、電子カルテでも周知できるようにしました。
- 新しく院内チーム医療としてRRT;Rapid Response Team(院内迅速対応チーム)が結成され、安全研修を実施したのち、RRS;Rapid Response System(院内迅速対応システム)が始動しました。
- 医療安全管理相互視察:2023年2月16日に中央市民病院及びアイセンターとの相互評価を実施しました。
- 令和3年度
-
- 画像診断既読管理システムCITA運用開始:放射線科医による画像診断の結果を、依頼した医師が確実にチェックできているかを監視するシステムを導入しました。
- 肺血栓塞栓症の予防:医療安全の観点から肺血栓塞栓症予防管理料算定の手順を見直しました。
- 生化学検査の不具合の迅速通知:検査機器のトラブルなどによる不具合が発生した場合の迅速な院内通知方法を整備しました。
- 診療科別のインシデント報告件数の集計:医師からのインシデント報告を促進するため、診療科別に報告数を集計し、報告することを開始しました。
- 令和2年度
-
- 患者さんが利用するシニアカー・電動車椅子に関する注意喚起を行いました。ポスターを作成し、事故防止のためシニアカーについては院内乗り入れ禁止としました。
- 当院における「包括同意」について病院ホームページに掲載しました。
- インスリン治療に関する医療安全強化のため、医療安全管理委員会に糖尿病チームの参加が実現しました。
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)院内感染対策のため、ディスポーザブルの救命救急用器具(バックバブルマスク)を配備しました。
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病棟開設に伴い、麻酔薬・鎮静薬の使用の検討を行いました。
- 不穏・不眠時の必要時指示薬の使用方法の徹底を行いました(リエゾン・認知症ケアチームと協力)。
- 救急外来における電子カルテのログアウト時間を厳密に設定しました。
- 令和元年度
-
- 患者間違いを防ぐ取り組みとして、患者さんの診察券にバーコードを付けました。
- 検査結果の重大な異常値(パニック値)があった場合の連絡体制を見直し、担当医師に確実に伝えることができるようにしました。
- 送信機の電池切れによる異常の発見が遅れた事例があり、セントラルモニタ送信機の管理を見直しました。
- 安全な透析が実施できるよう体重測定の手順を見直しました。
- 重複投薬や手術、検査への影響を鑑み、持参薬管理を見直し、HCU、救急病棟に入院の患者では持参薬の使用は原則禁止としました。
- 気管挿管処置時に投与する筋弛緩薬の管理をより厳重にしました。
- 正確な判断、記録を行うために、医療機器を含む院内の時計の時間合わせを徹底するようにしました。
- 包括同意に関する文書を作成し、一般の検査や処置に対する説明・同意を得るようにしました。
- 平成30年度
-
- お薬手帳の自動読み取り機を導入しました。
- 電子カルテ終了と画像PACS終了を連動させ、患者画像が残らないようにしました。
- 医療安全マニュアルのポケット版を作成しました。
- 人工呼吸器装着患者の搬送マニュアルを見直し、看護手順を改訂しました。
- 院内処方薬のうち、中止薬を病棟からの引き上げました。
- 医療事故調査制度への対応として、死亡診断書作成時に死亡報告書を追加作成する運用としました。
- 病院機能評価受審後に、行動抑制のマニュアルを改訂しました。インシデントの事象レベルを全国レベルと同じにしました。
- 平成29年度
-
- ベッド柵が金属腐食のため破損し、転落・転落事故にいたった事例があり、劣化したベッド部品などの見直しを実施
- 手術部で抗生剤ラベル発行に関するインシデントが多発したため、クリニカルパスでの注射オーダにおいて、対象となる68項目の投与方法を変更し、手術時注射となるようにした。その後、同様のインシデント発生はなくなった。
- 人工呼吸管理中の患者への吸入気管支拡張薬メプチンエアー®の投与方法に関するインシデントがあり、人工呼吸器の接続デバイスを変更した。
- 食物禁忌食材を提供したインシデント(事例はサバ)があり、入院時にアレルギー情報をFAXで栄養管理室へ連絡する運用とした。あわせて患者基本情報へのアレルギー情報の登録を徹底するようにした。
- 安全パトロールの結果、手術室、放射線科などで、医療ガス(酸素ボンベと二酸化炭素)の保管が混在しており、医療ガスの表示方法を徹底した。
- 産科婦人科予定入院にも、「お薬外来」の適応を開始した。
- パーキンソン病患者に対し、禁忌薬であるセレネースが必要時処方されるインシデントがあったため、処方画面での注意喚起タブを設定した。ニューズレターでも周知を促した。
- 平成28年度
-
- 接触感染や空気感染の危険性のある患者に対する画像検査オーダーにおける感染症情報コメントの追加
- 医師のインシデント報告の推進、合併症報告の基準作成
- 放射線防護、造影剤使用・MRIに関する注意喚起
- 平成27年度
-
- 「静脈血栓塞栓症対策ガイドライン」改訂
- 医療事故調査制度に伴う医療安全管理マニュアル改訂
- 手術ならびに観血的検査・治療前の中止薬管理指針作成
- 「おくすり確認外来」における入院前常用薬チェックの開始
- 「西市民病院における診療拒否に関する対応指針」の作成
- 平成26年度以前
-
- 静脈注射実施マニュアルの改訂:「看護師が直接静脈注射してもよい薬品リスト」の作成
- 4階病棟でのピクトグラムの試験的導入
- 薬剤師の病棟配置による医薬品安全管理の推進
- 末梢静脈穿刺に伴う神経障害発生時の対応指針
- 救急カート内配備薬品のレイアウトの見直し・統一
- インスリン管理ファイルの作成・活用開始
- 鎮静処置を要する検査・処置に関する安全管理上の取り決め作成
- 「産科危機的出血への対応フローチャート」の作成
- 緊急帝王切開対応手順の改訂と模擬訓練(レッドカイザー訓練)開始
- 「入院患者の自殺防止のためのガイドライン」の作成
- 酸素ボンベの残量確認表の作成・設置
- 「インスリン皮下注射の処方・取り扱い」マニュアル改訂
- 静脈血栓塞栓症ガイドライン(西市民病院編)の作成etc
その他
医療ガス安全管理委員会研修との共催(eラーニングで開催)、人工呼吸器・血液浄化装置・シリンジポンプなど医療機器の安全使用、心肺蘇生法の研修など、医療安全に関連する部門別研修会を実施しています。

患者・家族の方々へお願い
医療の安全を高める取り組みは、単に医療者の注意や知識・技術の向上だけで成り立っているのではありません。患者さん自身の協力や、場合によって家族の方々の協力があって初めて確保できる安全も少なくありません。当院では患者さん自身や家族の方にも医療に積極的に参加をお願いしています。医療の安全を高める取り組みにも積極的にご協力ください。
患者間違い防止のために
外来診察や検査室では、患者さん自らお名前を名乗っていただくようお願いします
こちらからお呼びしたお名前の聞き間違いや、同性によく似たお名前の患者さんでの間違い事例が過去にありました。そのため、外来診察や検査室では番号表を発行し、フルネームの確認だけでなく、患者さんに自ら名乗っていただくようにお願いしています。
入院の際には、ネームバンドの装着をお願いします
入院患者さんには特別な場合を除いてネームバンドの着用をお願いしています。
カルテ(診療録)や診察券などでの患者氏名の確認だけでなく、入院患者さんの場合にはネームバンドによる患者確認を推進していますのでご協力をお願いします。
転倒・転落防止のために
入院中に患者さんが転倒したり、ベッドから転落することは、決してまれではありません!
転倒・転落は入院中にも起こりやすい事故の一つです。 普段とは違う環境や体調の変化で、思いがけなく転んだり、ベッドから落ちたりすることがあります。 軽い打撲程度で済む場合がほとんどですが、時に骨折や脳出血などをきたして手術を必要としたり、ごく稀に死亡事故につながることもあります。
当院では入院患者さんが転倒や転落を起こす危険性を評価し、患者さんや家族の方に転倒・転落防止対策の必要性を説明して協力をお願いしています。
過信は禁物です!歩行や移動に不安があれば、看護師をお呼びください
トイレへの移動などで看護師を呼ぶのをためらう患者さんも多く、一人で動いて転倒する患者さんが後を絶ちません。歩行や起立、移動に少しでも不安があれば、ナースコールで看護師をお呼びください。
家族の方から見て不安があれば、医師や看護師にご相談ください
自宅での状況も含めて、患者さんをよく見ておられる家族の方からの情報はとても大切です。家族の方から見られて不安に感じられる部分があれば、医師や看護師にお伝えください。
必要に応じて、家族の方の付き添いをお願いします
認知症やせん妄症状のある方だけでなく、入院中の患者さんの多くに転倒や転落の危険性が潜んでいます。出来るだけ安全に配慮して対応しておりますが、それでも危ない場合には、必要に応じて家族の方に付き添いをお願いしています。
薬の処方・服用の間違い防止のために
入院の際には、薬剤師が服薬歴や持参薬のチェックを行います
薬の重複処方を防ぐだけでなく、薬の相互作用による弊害を防ぐために、他病院でも薬の処方を受けられている場合は、必ず主治医・担当医や看護師、薬剤師にお伝えください。
血液を固まりにくくする薬(抗凝固剤、血小板凝集抑制剤など)を服用されている方は検査や手術などの前には必ずお知らせ下さい。
最近は、動脈硬化等に伴う血栓形成を防ぐ目的で、抗血小板剤や抗凝固剤を服用されている患者さんが増えています。出血を生じる可能性のある検査や処置、手術においては、安全のために服用を中止していただくことがありますので、前もって担当医や看護師にお知らせください。
但し、服薬を中止できない場合もありますので、自分の判断で中止しないようにお願いします。
薬にアレルギーのある方は、必ず担当医や看護師、薬剤師にお知らせください。
安心できる病院の診療環境・療養環境を守るために
暴言・暴力・セクシャルハラスメントなどは犯罪です。また、院内のルールはお守りください。
暴力・暴言などで他の患者さんにご迷惑がかかる場合や医療者の診療行為が妨げられる場合には、たとえ患者さんであっても診療をお断りしたり、中止することがあります。入院中の患者さんの場合には退院を命令することがあります。また、必要に応じて警察へ通報することがありますので、あらかじめご了解ください。これらは患者さんだけでなく、ご家族や友人の方々の行動であっても同様に対処させていただきます。
これらの行為は酒酔いなどを理由に免罪されるものではありません。暴力だけでなく、数々の暴言や威嚇行為が、患者さんのために働こうとしている医療者に不安と恐怖を与え、診療の妨げになっている実情をご理解下さい。
〒653-0013
神戸市長田区一番町2丁目4番地
 地図で見る Tel: 078-576-5251
地図で見る Tel: 078-576-5251
Fax:078-576-5358(代表)/ 078-579-1943(病診連携室 ※診療情報提供書送付先)
 地図で見る
地図で見る
-
病院案内
- 院長あいさつ
- 病院概要 基本理念・方針・沿革
- 患者の権利と責務、医の倫理
- フロアマップ、快適な環境づくりについて
- 包括同意について
- 医療安全の取り組み
- 交通アクセス
- 当院の特長(取り組み)
- 病院情報の公表
- 臨床データの研究利用に関するお願い
- ご寄付のお願い
- 一般社団法人National Clinical Database (NCD)の 事業への参加について
- 臨床評価指標
- 適切な意思決定に関する指針
- 医療費後払いサービス
- 院内フリーWi-Fi
- 厚生労働大臣が定める掲載事項
-
当院のがん診療について
-
外来のご案内
- 初めて受診される方へ
- 診療の流れ
- 診察週間予定表
- 救急診療のご案内
- 検査のご案内
- セカンドオピニオン外来のご案内
- Web予約システムのご案内
- 患者サービス向上の取り組み
- 予約制・紹介制のご案内
- 診断書・証明書について
- 治験・臨床試験について
- 病理解剖(剖検)についてのお願い
- 宗教的理由等による輸血拒否に関する当院の方針
- かかりつけ医について
-
入院のご案内
-
診療科・部門のご案内
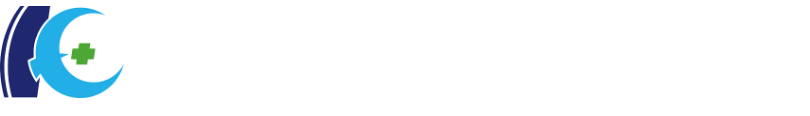




 救命救急外来の受付は24時間行っています。
救命救急外来の受付は24時間行っています。
