
疾患・症状説明DISEASE
発熱
体温・発熱の話
コロナ禍で体温測定が日常となりました。それに合わせるように総合内科の外来には「熱がさがらない」患者さん(病気ではないかと思っている人)の頻度が増えているように感じます。さらには「熱っぽいのが取れない」「いつも微熱があって普段より2、3分(0.2〜0.3度)高いのが心配」となると なかなか微妙な変化です。
日常生活で温度を話題にするとき単位はまず1度刻みです。「冷房は環境に気をつけて26.3度に設定している」とは言いません。
「体温」は違います。我々人類を含む哺乳類の体の内部の温度は、脳や心臓などの大切な臓器の働きを保つために非常に厳密に調整され安定しています。この体の内部の温度を「中枢(核心)温」といい、これを測れば、安定した「体温」が得られます。しかし、体の内部なので、日常的に測ることは困難です。(医学的には特殊な機器を用い 食道温、肺動脈温、膀胱温さらには脳温などを測定し治療に役立てています)そこで、より体内の温度が反映され、体に負担をかけずに簡単に検温できる部位として、ワキ(腋窩)、口(舌下)、耳(鼓膜)、まれには肛門(直腸)などの場所が用いられています。
鼓膜温と直腸温は核心温に近い温度を示すと考えられ、腋窩温と口腔温はより体表に近い温度を示し外核温と呼ばれます。外核温を測定する医療機器を一般的に「体温計」と呼びます。体温計は計量法において適正な計量の実施の確保のために検定などの制度で規制される特定計量器の1つで検定証印又は基準適合証印が付されているもののみが「体温計」として販売できます。(経済産業省 計量法における計量器の規制の概要 参照)
体温計(*1)
- 体温を計るのは難しい
今、水銀体温計を使用する人は居ないのではないかと思います。若い方は使い方(水銀のリセットの仕方)を知らないかもしれません。病院でも体温計は全て電子体温計です。
現在電子体温計は実測式と予測式があります。
実測式は文字通り平衡温に達するまで測定して実際の温度を表示します。(10分程度の時間がかかり、お知らせの合図がなるまでに止めてしまうと不正確な数字になります)
予測式は1分足らずで測定完了の合図がなりますが、表示される温度は実際に測定された温度ではなく温度上昇カーブから推定される平衡温を表示します。予測される温度の精度は平均を取ると実際の平衡温との差は0.01度と非常に正確ですが、ばらつき(標準偏差)は0.13度とかなり大きくなります(誤差は−0.13度と+0.13度の間に約6割が入ると言う意味です。9割の値が入るようになるには上下0.26度 約0.5度の幅のばらつきが出ます)
予測式の体温計でも最初の合図(予測ができたとの合図)を無視して測り続けると実測式に自動的に切り替わる機能がついていることが多く10分ほどでもう一度合図があって平衡温となったことを知らせてくれて体温が実測できます。大きな差ではありませんが、0.2度程度の微熱(体温上昇)が気になる方は実測式として使用する必要があります。
予測式を使用する場合はワキ用(腋窩温測定用)か口腔用(舌下温測定用)で予測式が変わるのでワキ用の体温計を口に含んで測ってはいけません(長く入れて実測式として使用することはできます) 腋窩温と舌下温は平均で若い女性(研究の被検者が女子大の学生であったため)では0.1度ほど舌下温が高くなります。(*2) また平衡温になるまでの時間も舌下温が短く、測定ごとのばらつきも少ないとされています。
日本では腋窩温が測定されることが圧倒的に多いのですが、欧米ではもっぱら舌下温です(外国映画で体温測定のシーンは口に体温計を突っ込まれているのを見ます)他人と共用することを考えると消毒しているので問題はないのですが、人の脇と口とどちらが嫌かといえば微妙な選択です。
参考
- 非接触体温計(温度計)
オデコでぴっ と計る体温計です。上記の特定計量器には含まれませんが、認定制度があります。
しかし世の中には医療機器として認定されていないものも出回っています。「非接触温度計」とか「非接触体表温計」とか「非接触検温計」と表示され「体温計」とは書かれていないものは非認定のただの「温度計」です。(認定されていない機器に「体温計」と表示すると違法になります)
また認定されている非接触体温計も「体温」と表示される温度は「額の皮膚温」と「室温」から演算式で計算される推定腋窩体温もしくは推定舌下体温であって実測値ではありません。さらに正しい測定方法は機器と被験者が同一の安定した室内に20分ほど居て、おもむろに測定を始めなければなりません。外から入ってきて「体温測定をお願いします」「ピッ」では何を測った解らない数字を「○○度ですね はい、大丈夫です」とお互い納得しているだけです!
- サーマルカメラ
建物の入り口にあるモニターに写った顔に四角い枠が表示され、何やら36.○ 35.○と数字が並んでいるものです。AI機能が搭載され顔認証を行い認証された範囲の表面温度を表示しています。じっと画面を睨んで「熱はないな」と呟いている方がいますが、体温計ではありませんので発熱を判定することはできません。
いずれもたくさんの人を短時間に測定し判断するために利用するもので個人で使用するものではありません。発熱している人を割り出すことはできませんが、決して「格好だけ」で置いているのではなく「高熱の患者さん」を特定するために利用します。
平熱
- いつもの私の「体温」てなに?
UpToDate(ネット上に展開されている2次医学情報・7,300名以上の執筆者と編集者が専門知識を駆使して文献を厳密に評価し、エビデンスに基づき執筆した12,000件以上のコンテンツ)の平熱の項には35.2〜37.7度 平均36.7度(35000人以上の約250000回計測した口腔内(舌下体温)体温 99%範囲(3SD)は35,3~37.7度)(*3)さらには別の論文では35.4~37.7度 (約44000人 500000回計測 口腔内体温)(*4)
さらに詳細な研究では、
35.6~38.2度 平均36.8±0.4度 (148人を700回計測 口腔内体温)(*5)思っているより高い印象があると思います。
日本人の研究ではワキ(腋窩)温度で36.89度±0.34度(10~50歳の男女3,094名、検温時間30分)とされており、36.6~37.2度の間に入る人が、全体の概ね68%を占めます。±2SDで示される正常範囲は36.2〜37.6度になります(※6)。
一方、高齢者の体温は約0.2度ほど低く、36.66度±0.42度とされています(65歳以上男女2,470名)(※7)。
かなり古いデータで現代の日本人はもっと低いという人もありますが、欧米のデータは最近の論文ですし、腋窩温と舌下温は上述のように0.1度差です。 新型コロナ感染症が当初問題となったとき発熱は37.5度以上とされ、違和感を持った方も多いと思いますが、このようにデータに基づいて決定されたと言えます。
(ただし数字自体は感染症法で37.5度以上が発熱、38度以上が高熱と定められていることに由来します。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について<別紙<医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準<第1 全般的事項<2 発熱と高熱<本基準において、「発熱」とは体温が37.5℃以上を呈した状態をいい、「高熱」とは体温が38.0℃以上を呈した状態をいう と記載されています)
これらの平熱の値は研究として厳密に測定しようとして得られたものです。何気なく測った体温はいい加減とは言いませんが、きっちりと測定したものでは無く一般的に低く出がちです。たまたま正確に測れて「あれ高い」となって繰り返し測り始めると、しっかり測定するようになって正確な値が出続けることになるのかもしれません。
体温変動
- 体温は常に変動している
人には、朝・昼・夜と、24時間単位に体温が変化する体温リズム(概日リズム)があります。1日のうちで早朝が最も低く、次第に上がり、夕方に最も高くなり、約1度の差があるとされます。

さらに閉経前の女性は月経周期に連動して体温が変動することが知られています。昨年、日本人女性31万人、600万月経周期のビッグデータを解析し、月経周期や基礎体温が年齢により変化することが明らかになりました。基礎体温について、低温期(卵胞期)の平均体温は年齢変化がなく36.4度でほぼ一定でしたが、一方高温期(黄体期)の平均体温は10代から20代後半にかけて徐々に上昇し、29歳で36.7度まで上昇した後に30代では安定し、42歳を過ぎると下降することが分かりました。また基礎体温は卵胞期・黄体期ともに季節変動を示し、夏に高く、冬に低くなることが明らかになりました。(*8)
また、これとは別に男女共に季節的変動があると記載されてきましたが、普遍的な規則性ははっきりしていません。
体温の調整と発熱の機序(*9)
- 体温を理解するのはとても難しい
脳の中には体温調節を司る体温調節中枢が存在するとされています。
現在の脳科学では視床下部の最吻側に位置する視索前野に存在することがわかっています。そこに深部体温センサー(視索前野付近にあって脳組織温度が上昇することにより興奮する温ニューロン)と末梢温度センサー(主に皮膚温度)からの情報がもたらされて統合され、それに基づいて適切な体温調節反応の種類と強度が決定され、出力されるという考え方が主流だそうです。
熱産生反応は交感神経系の強い支配を受ける褐色脂肪組織でおきる代謝性(非ふるえ)熱産生と体幹運動神経を介した骨格筋でのふるえ熱産生(シバリング)とがありますが、体温調整中枢はその熱産生を惹起する延髄自律神経中枢に対して継続的抑制的に作用しており、その破壊(重篤な脳内出血などで視床下部が障害をうけるなど)により熱産生が暴走して高度の高熱症に至ることが知られています。
発熱は炎症性サイトカインが脳内に到達することにより脳内のプロスタグランジン(PGE2)産生が高まり、その働きによって結果的に視索前野のニューロンが抑制され(温ニューロンの発火が減少する)ることにより体温調節中枢の抑制作用が弱められ熱産生が増加すると考えられています。解熱剤はそのプロスタグランジンの産生抑制の作用があり、それにより熱産生を抑制し解熱効果を得ることができます。
ただし実際の体温が設定されるメカニズムについては不明なことが多く「どのようにして正常体温が37°Cに設定されているのか?」という重要な疑問には今は答えることができません。
発熱と新型コロナ感染症
- 新型コロナウイルス感染症は熱を目印にすると危ない
やっとコロナの話に戻ってきました。
コロナウイルスは風邪の原因ウイルスの1つであり新型コロナウイルス感染症でも初期症状は風邪の症状で主で発症者の8割以上で発熱が見られます。
しかし新型コロナウイルスは狡猾で無症状の感染者が4割ほどあり、その無症状感染者からも他の人に感染します。図は和歌山県からの報告です。和歌山県は新型コロナ感染症に罹患した人を丁寧に追跡し詳細な報告を行っている県です。それによると陽性判明時には7割の人が37.5度以下で経過中に一回も発熱しない患者さんも5割以上となっています。熱を目印に新型コロナ感染症を防ぐことはできないのです。そのため、病院では全ての人が感染者の可能性があるものとして不織布カスクを着け手指消毒をすることをお願いしています。

毎日新聞 和歌山版より引用
参考
- *1 テルモ 体温研究所のHP 体温計の基礎知識 を参考にしました 一部引用
- *2 日生気誌30(4):159-168,1993〕 (Jpn. J.Biometeor.30(4):159-168,1993)
- *3 BMJ 2017; 359:j5468.
- *4 JAMA 2021; 325:1899.
- *5 JAMA 1992; 268:1578.
- *6 日新医学 1957、44(12)、635~638頁
- *7 日老医誌 1975、12、172~177頁
- *8 Obstetrics & Gynecology online 2020;Sep.10
- *10 オンラインサイト 脳科学辞典 体温調節の神経回路 のページを参考にしました
〒653-0013
神戸市長田区一番町2丁目4番地
 地図で見る Tel: 078-576-5251
地図で見る Tel: 078-576-5251
Fax:078-576-5358(代表)/ 078-579-1943(病診連携室 ※診療情報提供書送付先)
 地図で見る
地図で見る
-
病院案内
- 院長あいさつ
- 病院概要 基本理念・方針・沿革
- 患者の権利と責務、医の倫理
- フロアマップ、快適な環境づくりについて
- 包括同意について
- 医療安全の取り組み
- 交通アクセス
- 当院の特長(取り組み)
- 病院情報の公表
- 臨床データの研究利用に関するお願い
- ご寄付のお願い
- 一般社団法人National Clinical Database (NCD)の 事業への参加について
- 臨床評価指標
- 適切な意思決定に関する指針
- 医療費後払いサービス
- 院内フリーWi-Fi
- 厚生労働大臣が定める掲載事項
-
当院のがん診療について
-
外来のご案内
- 初めて受診される方へ
- 診療の流れ
- 診察週間予定表
- 救急診療のご案内
- 検査のご案内
- セカンドオピニオン外来のご案内
- Web予約システムのご案内
- 患者サービス向上の取り組み
- 予約制・紹介制のご案内
- 診断書・証明書について
- 治験・臨床試験について
- 病理解剖(剖検)についてのお願い
- 宗教的理由等による輸血拒否に関する当院の方針
- かかりつけ医について
-
入院のご案内
-
診療科・部門のご案内
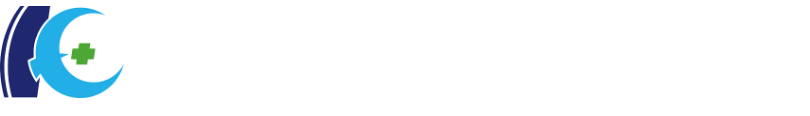




 救命救急外来の受付は24時間行っています。
救命救急外来の受付は24時間行っています。
