
診療科・部門のご案内DEPARTMENT
認知症疾患医療部(認知症疾患医療センター)
診療内容・特色
認知症疾患の鑑別を主体とした外来を実施しています。基本的には鑑別診断と薬物治療導入までの診療を実施し、かかりつけ医の先生にお返しします。また、2018年10月より認知症疾患医療センター、2019年より神戸市による認知症診断補助制度の2次検診機関として活動しております。
診断までの流れ
問診・診察
具体的にどんな症状がいつ頃からあるのかをお尋ねします。どういった認知機能が低下しているのか、問診とともに診察を実施いたします。
また生活の中で出来なくなったことがあるかお尋ねします。金銭管理はできるか、買い物での品物選び、支払いができるか、料理はできるか、掃除洗濯はできるか、携帯電話など電化製品を使えるか、くすりを飲んでおられるなら自分で管理できているか、着替えはできているか、入浴はできているかといったことをお尋ねしています。
家での様子は診察室で把握できませんので、ご存知の方(ご家族様)との受診をお願いしております。
神経心理検査
MMSE、MoCA-Jなどを行います。別の日にADAS-Jcogなどを実施することもあります。
診断に関して


認知症を来たす脳疾患には、アルツハイマー病や脳血管障害、レビー小体病などがあります。
受診いただいた方の診断内訳は下図のようになります。(令和4年度実績)

治療・地域連携に関して
基本的には認知症疾患診療ガイドライン2017にのっとっての治療を実施しています。
なお、認知症の行動・心理症状(BPSD:暴言や暴力、興奮、抑うつ、不眠、昼夜逆転、幻覚、妄想、せん妄、徘徊、もの盗られ妄想、弄便、失禁など)の治療目的での受診の場合は、基本的には精神神経科医師にお願いしております。
非薬物療法として、兵庫県音楽療法士会様にご協力いただき音楽療法を実施しています。
その他、治験に参加するなど新規治療法にも積極的に取り組んでいます。
また院外の多職種の方々と事例検討会等を実施しています。

音楽療法の様子
教育に関して
患者様、家族様向けの勉強会を実施していますが、現在は休止中です。
医療従事者向けに認知症対応力向上研修やオープンカンファレンス等を実施しています。
日本認知症学会専門医教育施設認定(2022年1月認定)です。

認知症対応力向上研修の様子
その他
アルツハイマー病については、その原因となるアミロイドは認知症になるより25年も前から脳にたまると言われているので、若い頃から対策が必要です。認知症リスクを減らすためにも以下のことが大事と考えています。(参考:The WHO Guidelines on risk reduction of cognitive decline and dementia)
- 運動しましょう
- タバコはやめましょう
- バランスよく栄養をとりましょう
- アルコールはひかえましょう
- 頭を使いましょう
- 社会参加しましょう
- 体重に気をつけましょう
- 血圧に気をつけましょう
- 糖尿病に気をつけましょう
- 脂肪やコレステロールに気をつけましょう
- 楽しく過ごしましょう
- 難聴に気をつけましょう
その他、(薬に頼らない)自然な睡眠を十分にとることも大事であろうと思います。睡眠中に、前述のアミロイドが脳から排出されるのではないか、という報告もあります。
認知症となっても安心して過ごすことのできるまちであることは重要であり、そのための活動をしていきます。 一方で、認知症となりにくい生活習慣も重要なことであり、啓発していきたいと考えています。
認知症疾患医療センターの紹介

認知症疾患医療部(神戸市認知症疾患医療センター)の組織図
神戸市より指定を受け、認知症の診断、治療、医療、生活、介護の相談、地域の関係機関との連携や研修を行う専門医療機関です。
事業内容
- 鑑別診断、治療方針の選定
- 身体合併症・周辺症状への急性期対応
- 専門医療相談
- 認知症家族会の開催
- 域保健医療介護関係者への研修
- 進行予防事業の実施
- 地域への情報発信・広報・啓発
- 認知症疾患医療センター地域連携会議の開催
認知症早期発見のメリット
- 将来に備えることができます
初期の認知症であれば、治療や介護サービスを選び、これからの生活についてお願いする人をご自身で 決める等、今後の人生の準備ができます。 - 病気の原因によっては、治療が可能です
正常圧水頭症、慢性硬膜下血種などが原因であれば、認知機能も改善する可能性があります。 - 症状の進行対策が考えられます
服薬・生活習慣の改善・適切なケアなどで、認知機能を長く保つ方法もあります。
専門医療無料相談(電話・面談)
専門の職員(保健師、精神保健福祉士、看護師など)が認知症に関係する相談を受けます。
面談での相談をご希望の方は電話での予約が必要です。
認知症疾患医療センター専用電話:078-579-1966
受付時間:9時〜17時(土日祝日、年末年始を除く)
- ちょっと忘れっぽい、何度も同じことをいう
- 約束を忘れる、道に迷う、しまい忘れがある
- 元気がでない、怒りっぽくなり性格が変わった
- 介護の相談をする場所が知りたい・どこにどんな相談をして良いかわからない
- 受診したいが方法がわからない
医療従事者のための認知症対応力向上研修
認知症の人や家族を支える院内外のスタッフに向けて、医療従事者のための認知症対応力向上研修を開催しています。医療従事者だけでなく、地域のケアマネジャー、看護職の方々も参加いただいています。毎年、趣向を凝らした内容を企画しており、2019年度は外部講師を招いて「認知症高齢者とのコミュニケーション方法」について学ぶ機会とし、地域のスタッフが困る事例についてワールドカフェ方式により多職種で意見交換しました。参加者からは、認知症患者さんの行動、言動に理由を考える大切さがわかった、自分の感情・思いを変えていけそう、多職種の悩みや取り組みを知ることができたという感想をいただき、学んだことを活用できると評価をいただいています。(現在、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため休止中)
音楽療法の開催
認知症疾患医療センター主催で音楽療法を開催しています。音楽療法は、脳の活性化やリラクゼーションを目的にしており、外来患者さんだけでなく、入院患者さんが参加できる会を催す場合もあります。
認知症の理解の促進
市民公開講座、長田公民館秋季講座などを通じて、地域における認知症の理解の促進を図ります。
資料集
認知症疾患の診療について、当センターの考え方、診療時の参考資料などをまとめております。ご参考になりましたら幸いです。
スライド
| No. | タイトル | 内容 | 資料作成日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 認知症リスクを下げる生活習慣WHOガイドラインから | 認知機能低下・認知症リスクを減らすために取り組んでいただきたいことなどをまとめたスライドです。 | 2022/01/27 |
| 2 | 対応の仕方についてのヒント | 認知症の家族がいる方や介護する方が認知症の方と接する際に参考となる知識(認知症の方の行動要因、認知症の方への接し方)をまとめたスライドです。 | 2022/01/27 |
動画
| No. | タイトル | 内容 | 資料作成日 |
|---|---|---|---|
| 1 |
市民公開講座「認知症への備え」 |
2024/01/04 | |
| 認知機能低下・認知症リスクを減らすために取り組んでいただきたいことなどをまとめた動画です。 | |||
| 身近な人が認知症になったらどうしたらよいかなどを説明しています。 | |||
| 食事で注意してほしいことや栄養バランスの良い食事に改善するためのヒントなどをまとめています。 | |||
| 名前 | 木原 武士 |
|---|---|
| 役職 | 部長(脳神経内科部長 兼務) |
| 卒年 | 平成4年 |
| 専門分野 | |
| 認定医・専門医・指導医 | 日本認知症学会専門医・指導医 日本神経学会専門医・指導医 日本内科学会認定内科医 日本内科学会総合内科専門医 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 |
木原 |
木原 認知症鑑別(要予約) 10:00から |
木原 |
木原 |
- |
| 午後 |
木原 |
木原 認知症鑑別(要予約) |
木原 認知症鑑別(要予約) |
木原 認知症鑑別(要予約) |
- |
【備考】
認知症鑑別は予約制
診察は精神・神経科2診で行います。
治療症疾患に関して
治療方針
認知症では疾患そのものにより生じてくる症状、つまりすべての患者に共通の症状と、BPSD (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)、「認知症の行動・心理症状」と総称される症状とがあります。
特にアルツハイマー病では、記憶障害(記銘力障害)や見当識障害(日付や場所、人物の認識)、実行機能(計画を立てる、段取りをつけるなどの能力)の障害などの中核症状を基礎に、不安やストレス、疎外感といった因子が加わってくると、BPSDすなわち徘徊・攻撃・暴言・暴力・拒絶・収集などの行動障害や、興奮・幻覚・妄想・せん妄・不安感・鬱状態・不眠などの精神症状が生じることがあります。
治療には薬物療法と非薬物療法および介護・ケアがあり、いずれもが重要です。

非薬物療法
1)認知症のひとへの対応
認知症のひとの多くは高齢者でもあり、生活歴や環境、他の身体症状を抱えていることで、症状が変動することあります。基本的な接し方としては、認知症のひと自身のはなしをよく聞いて、安心感を与えてあげること、「だいじょうぶ」と思える環境にしてあげることが必要と考えております。
なじみの暮らしの継続
生活環境の変化、在宅から施設入所や入院を契機に症状が悪化することがあります。新しい環境に適応することが困難であることから、なじみの物の調整をする、認知症のひとの慣れ親しんだ生活が続けられるように環境を整える、なじみの人間関係をつくるといった工夫を実施することが望ましいと思います。
以下の各メソッドは研修を受けた実践者が行うとされていて、詳細についてはここでは触れません。
認知症のひとへの対応にあたり参考になると思われることについてご紹介します。
パーソンセンタード・ケア
認知症をもつ人を1人の人として尊重し、その人の視点や立場に立って理解し、ケアを行おうする考え方です。疾患、性格傾向、生活歴、健康状態、心理・社会的背景などの多様な面から捉えて認知症のひとの行動や状態を理解します。
主体性と自己決定を尊重し、出来るだけ自分のことは自分で行っていただきます。慣れ親しんだ環境下で生活することも大事です。
バリデーション(確認療法)
認知症のひとの世界を否定せずに感情を共有し、言動の背景や理由を理解しながら関わる手法です。会話を確認・受容することで安心感を促進する。混乱した行動には理由があると考え、混乱した考えにも受容と共感の対応を示します。
ユマニチュード
フランス語で「人間らしさ」を意味する「ユマニチュード(Humanitude)」では、対象の「人間らしさ」を尊重し、各人の状態に応じたケアを提供します。ケアの際には「見つめること」、「話しかけること」、「触れること」、「(本人が)立つこと」の4つの柱を重視し、「ケアする人とは何か」、「人とは何か」と言う命題を根底にした知覚・感覚・言語によるコミュニケーションメソッド。「回復を保つ」「機能を保つ」「共にいる」の今の段階を評価することから始めます。ケアを受ける人に「あなたを大切に思っています」「あなたはここにいます」というメッセージを伝えます。
その他
行動異常と周囲がとらえる行動であっても、目前の状況に応じて認知症のひと自身が選んだ行動です。そのため原因となる状況・環境の整備が、混乱した行動を避けるために必要と思われます。
2)リハビリテーション
神経変性疾患による認知症では、基本的には症候が進行することから、認知機能を高めるためのリハビリテーションを行っても認知症のひとでは目立った改善がみられず、かえって苦痛を感じることがあるかもしれません。そのため、セラピストあるいは仲間とコミュニケーションをとりながら楽しい時間を過ごすことで、意欲を高め、残存機能を維持することが望ましいと思います。
当院では、一部の方のみを対象としておりますが、音楽療法、回想法を実施しております。
- 回想法
過去の懐かしい思い出を語り合ったり、誰かに話したりすることで脳が刺激され、精神状態を安定させる効果が期待できます。子どものころ遊んでいたおもちゃ、昔の写真、若いころに流行していた映画や音楽などの道具を用意し、必要に応じて問いかけをしながら、思い出話に耳を傾けます。周囲が認知症のひとの話を傾聴し、その人生を肯定的に評価・受容していくことで心の安定をはかります。 - 音楽療法
歌唱活動、鑑賞、楽器活動、音楽回想法などがあります。強いリズム、またははっきりとした曲調で行うことで、体内リズムが同調し、手拍子や足などの体の動作を誘導することができます。また歌を通して、その流行した当時を回想することが遠隔記憶への刺激や自己表現・感情表現の促進にもつながります。 - 認知機能訓練
- 認知リハビリテーション
- 認知刺激
- 運動
などの方法があります。詳細は省かせていただきます。
薬物療法
当院では、基本的には認知症疾患診療ガイドライン2017に沿っての治療を実施しています。
1)アルツハイマー型認知症中核症状の治療薬について
アルツハイマー型認知症の場合、アセチルコリンを用いて情報を伝える神経細胞(コリン系)が特に減少しています。このコリン系は認知機能に関連すると考えられています。アセチルコリンの分解を抑制することを目的に開発されたのが、コリンエステラーゼ阻害薬 (ChEI) であるドネペジル塩酸塩、ガランタミン臭化水素酸塩、リバスチグミンとなります。
一方、メマンチン塩酸塩は、別の神経伝達物質、グルタミン酸が作用するN-methyl-D-aspartate (NMDA)受容体の拮抗薬です。
使用にあたってはガイドライン、当科作成のスライドをご参照ください。
2)BPSDに使用する薬剤について
BPSDに対応するに当たっては、患者本人や介護者の心理状態、環境、性格、行動パターン、人生観などの背景を検討することが必要と思います。また、起こりやすい時間帯や場所、前後の状況を検討することで引き金となることが何かを明らかとし、介護者全員で確認して一定した対応を行うことが望ましいと考えております。その上で,薬物療法を追加していくことが良いのではないでしょうか。
脳疾患そのものに直接関わる要因や心理学的要因に対する根治的治療法は確立してはいません。BPSDに適応をもつ薬剤も限られています。また、薬剤は運動機能、認知機能を障害する等の副作用をもつものも多いので注意が必要です。
使用にあたってはガイドライン、当科作成のスライドをご参照ください。
3)せん妄に関して
注意の障害および意識の障害で、 短時間で出現、経過中に変動する状態ですが、幻覚・妄想や興奮などを生じることから認知症疾患の症状ではないかと紹介されることがあります。もちろん認知症疾患で生じることもありますが、発熱など身体疾患や、薬剤、アルコールなどで起こることも多いです。
せん妄は認知症のリスクと考えられていますので、予防が大事です。薬剤の中でも、睡眠薬であるGABA受容体作動薬など中枢神経に作用する薬剤、ステロイド剤、鎮痛剤などがせん妄リスクを高めます。使用は必要最小限としていただくことが望ましいと考えております。
出現したせん妄に対しては、直接因子と誘発因子の治療、除去で改善しない場合には、非定型抗精神病薬による治療を行います。
使用にあたってはガイドライン、当科作成のスライドをご参照ください。
資料集
認知症疾患の診療について、当センターの考え方、診療時の参考資料などをまとめております。ご参考になりましたら幸いです。
スライド
| No. | タイトル | 内容 | 資料作成日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 認知症リスクを下げる生活習慣WHOガイドラインから | 認知機能低下・認知症リスクを減らすために取り組んでいただきたいことなどをまとめたスライドです。 | 2022/01/27 |
| 2 | 対応の仕方についてのヒント | 認知症の家族がいる方や介護する方が認知症の方と接する際に参考となる知識(認知症の方の行動要因、認知症の方への接し方)をまとめたスライドです。 | 2022/01/27 |
| 3 | 認知症の診断について | 認知症疾患診断ガイドライン2017などからどう考えて診断しているのかをまとめた概論的なスライドです。 | 2022/01/28 |
| 4 | アルツハイマー病の診断について | アルツハイマー型認知症の診断についての考え方を示したスライドです。詳細は成書等をご参照ください。 | 2024/02/17 |
| 5 | 前頭側頭型認知症の診断について | 前頭側頭型認知症の診断についての考え方を示したスライドです。詳細は成書等をご参照ください。 | 2022/01/26 |
| 6 | レビー小体型認知症の診断について | レビー小体型認知症の診断についての考え方を示したスライドです。詳細は成書等をご参照ください。 | 2022/01/26 |
| 7 | 血管性認知症の診断について | 血管性認知症の診断についての考え方を示したスライドです。詳細は成書等をご参照ください。 | 2022/01/26 |
動画
| No. | タイトル | 内容 | 資料作成日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 認知症疾患の薬物治療について、認知症疾患診療ガイドライン2017などからどのように考えて実施しているかをまとめました。 | 2021/12/26 | |
| 2 | 市民公開講座「認知症への備え」 | 2021/08/12 | |
| 認知機能低下・認知症リスクを減らすために取り組んでいただきたいことなどをまとめた動画です。 | |||
| 身近な人が認知症になったらどうしたらよいかなどを説明しています。 | |||
| 食事で注意してほしいことや栄養バランスの良い食事に改善するためのヒントなどをまとめています。 |
治験
実施中の治験
実施中の治験はありません。
これまでの治験実績
| 薬剤名 | 対象疾患 | 薬剤の作用秩序 |
|---|---|---|
| BPN14770 | 軽度アルツハイマー型認知症(目安はMMSE20以上) | PDE4D阻害を介したcAMP上昇、CREBリン酸化亢進によるシナプス機能・神経機能の亢進 |
- 診療科
- 看護部
- 薬剤部
- 臨床検査技術部
- 放射線技術部
- リハビリテーション技術部
- 臨床工学室(CE室)
- 栄養管理室
- 地域医療部
〒653-0013
神戸市長田区一番町2丁目4番地
 地図で見る Tel: 078-576-5251
地図で見る Tel: 078-576-5251
Fax:078-576-5358(代表)/ 078-579-1943(病診連携室 ※診療情報提供書送付先)
 地図で見る
地図で見る
-
病院案内
- 院長あいさつ
- 病院概要 基本理念・方針・沿革
- 患者の権利と責務、医の倫理
- フロアマップ、快適な環境づくりについて
- 包括同意について
- 医療安全の取り組み
- 交通アクセス
- 当院の特長(取り組み)
- 病院情報の公表
- 臨床データの研究利用に関するお願い
- ご寄付のお願い
- 一般社団法人National Clinical Database (NCD)の 事業への参加について
- 臨床評価指標
- 適切な意思決定に関する指針
- 医療費後払いサービス
- 院内フリーWi-Fi
- 厚生労働大臣が定める掲載事項
-
当院のがん診療について
-
外来のご案内
- 初めて受診される方へ
- 診療の流れ
- 診察週間予定表
- 救急診療のご案内
- 検査のご案内
- セカンドオピニオン外来のご案内
- Web予約システムのご案内
- 患者サービス向上の取り組み
- 予約制・紹介制のご案内
- 診断書・証明書について
- 治験・臨床試験について
- 病理解剖(剖検)についてのお願い
- 宗教的理由等による輸血拒否に関する当院の方針
- かかりつけ医について
-
入院のご案内
-
診療科・部門のご案内
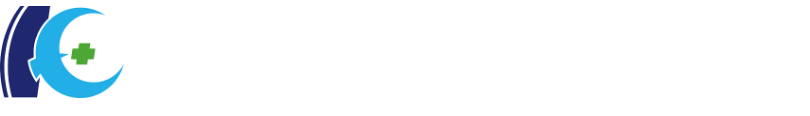




 救命救急外来の受付は24時間行っています。
救命救急外来の受付は24時間行っています。
