
診療科・部門のご案内DEPARTMENT
ICT(感染管理チーム)・AST(抗菌薬適正使用支援チーム)
ICT(感染管理チーム)・AST(抗菌薬適正使用支援チーム)
メンバー紹介
| 所属 | 職種 | 氏名【資格】 | ICT | AST |
|---|---|---|---|---|
| 総合内科 | 医師 | 王 康治 | 〇 | 〇 |
| 医師 | 小西 弘起【感染制御医師(ICD)】 | 〇 | 〇 | |
| 呼吸器内科 | 医師 | 藤井 宏 | 〇 | 〇 |
| 医師 | 瀧口 純司 | 〇 | 〇 | |
| 泌尿器科 | 医師 | 田代 裕己 | 〇 | |
| 医師 | 三田 淑恵 | 〇 | ||
| 皮膚科 | 医師 | 八木田 隼啓 | 〇 | |
| 総合内科 | 医師 | 濵﨑 健弥 | 〇 | |
| 呼吸器内科 | 医師 | 橋本 梨花 | 〇 | |
| 外科 | 医師 | 大越 祐介 | 〇 | |
| 外科(専攻医) | 医師 | 調枝 治樹 | 〇 | |
| 呼吸器内科(専攻医) | 医師 | 岩林 正明 | 〇 | |
| 総合内科(専攻医) | 医師 | 山本 大 | 〇 | |
| 消化器内科(専攻医) | 医師 | 中川 豪 | 〇 | |
| 研修医 | 医師 | 石川 佳奈 | 〇 | |
| 医師 | 久保田 雅哉 | 〇 | ||
| 看護部 | 看護師 | 俣木 陽子【感染管理認定看護師】 | 〇 | 〇 |
| 看護師 | 黒田 普美子 | 〇 | 〇 | |
| 看護師 | 泉谷 裕子 | 〇 | ||
| 看護師 | 大桑 由美 | 〇 | ||
| 薬剤部 | 薬剤師 | 嶋本 藍 | 〇 | 〇 |
| 薬剤師 | 山内 円 | 〇 | 〇 | |
| 薬剤師 | 宇都 早希 | 〇 | 〇 | |
| 臨床検査技術部 | 臨床検査技師 | 武元 優允 | 〇 | 〇 |
| 臨床検査技師 | 江上 和紗 | 〇 | ||
| 臨床検査技師 | 西山 茜 | 〇 | ||
| 医事課 | 事務職員 | 原田 梨紗 | 〇 | 〇 |
診療概要・特色
ICT
病床規模の大きい医療機関(目安として病床が300床以上)においては、医師・看護師・検査技師・薬剤師から成る感染制御チーム(ICT)を感染対策委員会の下部組織として設置する事が義務付けられています。従って今では一定規模の病院で勤務経験のある方には馴染みの組織ですが、「ICTです…」と名乗って訪問するとにこやかに迎えられる事はほとんど無く、“えっ何(何か不都合な事が起こっている?)”と反応されます。令和2年度より、病院組織上感染管理室としても位置付けられています。
活動内容も感染対策マニュアルには・・・
【ICTの所掌事務】
- 院内感染状況の把握
- 抗菌剤の使用状況の把握と適正使用の推進および 広域抗菌剤の届出管理
- 院内ラウンドの実施
- 感染防止対策の実施状況の把握と指導
- サーベイランスの実施と評価
- 職業感染防止対策の推進
- 職員教育の実施と啓蒙活動
- アウトブレイク対応
- コンサルテーション活動
- 感染症治療に関する指導、評価
- 感染防止対策に関する指導、評価
- 感染防止対策に関わるマニュアルの素案作成
- 院内各部門との連携強化
- 患者・家族への対応
- 地域との感染対策の連携
- その他感染対策に関すること

個人防護具(PPE)着脱指導の模様
と記載されていますが、理解していても受け入れがたい活動をしていると思われている向きもあります。病院内で活動している横断的なチームは個人、職域の立場から少し距離を置いて動くことを求められていると理解していますし、ICTもその立場で下記の為に活動しています。
上記の一部は、AST(抗菌薬適正使用支援チーム)が2018年1月に発足し、活動を開始しています。
患者さんのため・・・
感染症治療の原則
①感染症か ②細菌感染症か ③感染巣は何処か ④原因細菌は何か を意識した診療が行われているかをモニターしています。医療の全てに一般的原則が有ります。一般的な方針と異なる個別的な方針に基づいて行われる治療もしばしば必要となりますが、その根拠は主治医が思案検討し記載する必要があります。ICTは根拠が曖昧と判断すれば一般的な方針を示し主治医に検討をお願いしています。
医療従事者のため・・・
病院は様々な病原体が存在する場所であり、医療従事者は常に感染の危険に曝されます。感染対策委員会の活動として抗体検査の実施、ワクチン接種を行なっているほか、ICTは実際の症例において医療従事者が感染すること予防し、更には感染を早期に察知する対策の立案と指導を行っています。
病院のため・・・
院内感染のアウトブレイク事例に即応し拡大を最小限に止めることを目標にしています。アウトブレイクを疑う基準としては、一例目の発見から4週間以内に、同一病棟において新規に同一菌種による感染症の発病症例が3例以上特定された場合です。過去にはICTの権限で職員の出勤の停止、更には患者さんの入退院の制限まで必要となった事が有りました。
他に他病院(感染防止対策加算1の2病院、加算2の6病院との連携)神戸市保健センター、市県の保健局と情報の交換を行っています。
未来の患者さんのため・・・
抗菌薬が患者さんに使用される(当初は軍人に対してのみ)ようになって70年と少し、全ての抗菌薬に耐性菌が出現し、新規の開発はほぼ止まっている現代では1世紀を経ずして抗菌薬の栄光の歴史は途絶え、以前の暗黒の時代に戻るのでは無いかと心配されています。感染対策を行っている人間の間では、抗菌薬の命運が尽きるのは明白で今は何処まで保たせるかの問題で有るとの危機感が強く有ります。この危機感を全ての医療従事者で共有して貰う為に、今後も活動を強化したいと思っています。
COVID-19・・・
当院ではいわゆる「第一波」の頃からCOVID-19患者の受け入れを行い、流行状況に合わせて病床数を増減させ、2021年4月時点で2病棟を専用病棟としてゾーニングを行い、多数の患者を現在も受け入れています。COVID-19入院のほか、発熱外来、行政検査への協力、入院待機患者への往診を行いました。
各部署が協力し上記のCOVID-19対応を行っていますが、特にICTでは院内での接触者の特定、聞き取り、隔離対策、濃厚接触者の判定と就業停止の勧告、入院患者のスクリーニング検査の結果解釈、患者配置の設定、クラスター対応など院内感染対策を主に行っています。
AST
2012(平成24)年度診療報酬改定により「感染防止対策加算」「地域連携加算」が新設されICTの活動が初めて保険収載されました。さらに2018(平成30)年4月に見直され「抗菌薬適正使用支援加算」が新設され、ICT の活動の一部がAST(抗菌薬適正使用支援チーム)として別組織と評価されるようになりました。
- 本院は感染防止対策地域連携加算(感染防止対策加算1を取得し、さらに年1回以上他の加算1取得施設による外部評価を受けている時に加算ができます)を算定している施設です。
- 医師・看護師・薬剤師・検査技師からなる抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌化学療法認定薬剤師が専従として活動しています。
- 抗菌薬適正使用支援チームは以下の業務を行なっています。
・広域抗菌薬等の特定の抗菌薬を使用する患者、菌血症等の特定の感染症兆候のある患者、免疫不全状態等の特定の患者集団など感染症早期からのモニタリングを実施する患者を設定して介入を行っています。
・感染症治療の早期モニタリングにおいて、前項で設定した対象患者を把握後、適切な微生物検査・血液検査・画像検査等の実施状況、初期選択抗菌薬の選択・用法・用量の適切性、必要に応じた治療薬物モニタリングの実施、微生物検査等の治療方針への活用状況などを経時的に評価し、必要に応じて主治医にフィードバックを行っています。(年間で1500回以上の介入を行なっています)
・適切な検体採取と培養検査の提出(血液培養の複数セット採取など)の指導や、施設内のアンチバイオグラムの作成など、微生物検査・臨床検査が適正に利用可能な体制を整備しています。(本院の血液培養2セット採取率は既に90%弱になっています)
・抗菌薬使用状況や血液培養複数セット提出率などのプロセス指標及び耐性菌発生率や抗菌薬使用量などのアウトカム指標を月一回に評価し報告しています。
・抗菌薬の適正な使用を目的とした職員の研修を実施しています。また院内の抗菌薬使用に関するマニュアルを作成しました。
・使用可能な抗菌薬の種類、用量等について定期的に見直し、必要性の低い抗菌薬について医療機関内での使用中止を提案します。(昨年は院内で使用できる経口第3世代セフェムを1種類に制限しました) - 抗菌薬適正使用支援チームが、抗菌薬適正使用支援加算を算定していない医療機関から、定例連携会で抗菌薬適正使用に関する相談等を受けていることも多くあります。
ニュースレター
準備中
院内感染対策のための指針
院内感染対策のための指針(2018年12月17日改訂)(PDF:248KB)
当院における菌種別薬剤感受性率
- 診療科
- 看護部
- 薬剤部
- 臨床検査技術部
- 放射線技術部
- リハビリテーション技術部
- 臨床工学室(CE室)
- 栄養管理室
- 地域医療部
〒653-0013
神戸市長田区一番町2丁目4番地
 地図で見る Tel: 078-576-5251
地図で見る Tel: 078-576-5251
Fax:078-576-5358(代表)/ 078-579-1943(病診連携室 ※診療情報提供書送付先)
 地図で見る
地図で見る
-
病院案内
- 院長あいさつ
- 病院概要 基本理念・方針・沿革
- 患者の権利と責務、医の倫理
- フロアマップ、快適な環境づくりについて
- 包括同意について
- 医療安全の取り組み
- 交通アクセス
- 当院の特長(取り組み)
- 病院情報の公表
- 臨床データの研究利用に関するお願い
- ご寄付のお願い
- 一般社団法人National Clinical Database (NCD)の 事業への参加について
- 臨床評価指標
- 適切な意思決定に関する指針
- 医療費後払いサービス
- 院内フリーWi-Fi
- 厚生労働大臣が定める掲載事項
-
当院のがん診療について
-
外来のご案内
- 初めて受診される方へ
- 診療の流れ
- 診察週間予定表
- 救急診療のご案内
- 検査のご案内
- セカンドオピニオン外来のご案内
- Web予約システムのご案内
- 患者サービス向上の取り組み
- 予約制・紹介制のご案内
- 診断書・証明書について
- 治験・臨床試験について
- 病理解剖(剖検)についてのお願い
- 宗教的理由等による輸血拒否に関する当院の方針
- かかりつけ医について
-
入院のご案内
-
診療科・部門のご案内
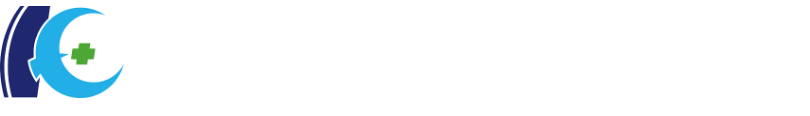




 救命救急外来の受付は24時間行っています。
救命救急外来の受付は24時間行っています。
