
診療科・部門のご案内DEPARTMENT
薬剤部
薬剤長のあいさつ
私たち神戸市立医療センター西市民病院 薬剤部は、患者さんのための医薬品であること、患者さんのための薬剤師である事を強く意識し、患者さんの傍ですべての患者さんに心のこもった最適な薬物治療を提供するために専門性を高め、医療チームとしてそれを活かしていきます。
そして病院だけにとどまらず、高齢化が加速度的に進む中でピンポイントの対応ではなく地域と連携し患者さんの治療をシームレスにサポートしていきます。

薬剤長 平畠 正樹
薬剤部の場所
西市民病院一階の正面玄関から入ると、右手に総合受付があります。その奥、左手すぐに薬剤部があり、「おくすり」の看板が目印です。三つの窓口(G~I)と指導室(J)の入り口があり、それぞれ、G「持参薬確認窓口」、H「おくすりお渡し窓口・持参薬確認窓口」、I「院外処方せん窓口・おくすり確認外来受付・薬剤師外来受付」、J「おくすり確認外来・薬剤師外来」となっております。薬剤部1階には、調剤室、注射室、医薬品情報室、患者指導室等があります。地下一階には、無菌(調製)室、製剤室、薬剤カンファレンス室等があります。

薬剤部正面の窓口と指導室入り口(右奥)
業務内容
1.調剤業務
処方は、電子カルテのオーダリングシステムから入力され、散薬や水薬調剤支援監査システム、錠剤自動分包機(一包化)システムが連動し、より安全かつ効率的に調剤を行います。薬剤師は相互作用、用法・用量、処方日数などをチェックし、疑問が生じた場合は直接医師に確認しています(疑義照会)。分包した粉薬や一包化した錠剤・カプセルの袋には患者名の他、薬品名や用法を印字し、患者さんやご家族が管理しやすいようにしています。


2.注射薬調剤

注射薬もオーダリングシステムから入力され、注射薬自動払出機(アンプルピッカー)が連動します。薬剤師は配合変化や投与速度、濃度、投与ルート等や、その他、調剤業務と同様のチェックを行い、必要に応じ医師に疑義照会を行います。注射薬は、患者ごと、1回使用ごとに注射トレイに入れ、患者さんの氏名、薬品名や量、用法などの他に3点認証コードを印字したラベル、および、看護師向けの注射薬に関する注意事項が記載された注射薬指示書を一緒に病棟の看護師に送ります。


3.ミキシング(混注)業務
抗がん剤は、静脈炎など一般的な注射薬と比べて血管のトラブルが多く、また病棟で抗がん剤をミキシングすると病棟スタッフだけでなく、患者さんにも抗がん剤が空気中に飛散して吸引してしまう(曝露)リスクはゼロではありません。薬剤師が薬剤無菌調製設備(アイソレータ:下写真)で抗がん剤のミキシングを専門的に行い、病棟における抗がん剤の曝露を無くすとともに、無菌的に調製を行っています。また、電子カルテに連動した抗がん剤レジメンオーダリングサポートシステムを用いてレジメンの一元管理を行い、さらに安全な投与管理、既往歴・配合変化・注射薬と内服薬を含めた複合的な相互作用などのチェックを行い、処方や検査の提案を行いながら医師と連携して、がん薬物療法を支援しています。


4.薬剤管理指導/病棟薬剤業務
-
1.入院時持参薬管理業務
当院ではすべての予定入院の患者さんと入院時に直接面談し、持参される薬の確認を行っています。薬の使用状況を全て確認(鑑別)し、今後の治療に影響がでる可能性がある場合は医師に報告し、処方提案を行います。その情報を電子カルテに登録し、入院中の薬物治療の支援を開始します。


-
2.病棟業務
全ての病棟に薬剤師が常駐し、医師や看護師、その他の多くの職種と連携しながら薬学的視点、患者さんの視点に寄り添って薬物治療を支援しています。またベッドサイドで患者さんと面談することにより、早期に効果・副作用を確認し、副作用は最小限になるように薬学的管理(薬剤アレルギー・効果・副作用などのモニタリング、使用方法の変更、相互作用のチェック、薬の中止・新規薬の医師に対する処方提案など)を実施しています。また今後、実施される薬物療法の予定、副作用を減らす(避ける)ための注意点などをお伝えしています。さらに個々の患者さんの使用目的に合わせたオリジナルのお薬一覧表を作成し、患者さんとご家族が薬物療法についてご理解しやすいように工夫しています。薬剤師全員が専用の電子カルテ端末と院内でインターネットが使えるiPadを装備し、臨床現場のニーズに対応しています。
5.医薬品情報業務(DI業務)
医薬品は情報が伴ってはじめて有効かつ安全に使用できます。常に最新の医薬品情報の収集・整理・伝達に努め、院内スタッフに提供することで薬物治療が適正に行われるようバックアップします。また、薬事委員会を通じて院内の情報発信の起点としての役割も担っています。その他、院内で発生した副作用の情報を随時、医薬品医療機器総合機構に迅速に報告を行い、国の副作用情報の収集にも協力するなど、医薬品情報にかかる種々の業務を行います。
6.薬剤師外来
医師の依頼に基づき外来の医師の診察前や後に専用の個室にて、薬剤師が外来患者さんと直接面談を行います。
1)おくすり確認外来業務
入院手術前に、薬や健康食品を事前に中止していなければ、入院・手術が中止になる場合があります。常用薬で手術前に中止するべきものがないか、健康食品・サプリメントに中止するべき成分が含まれていないかについてチェックするとともに、薬剤アレルギーの有無、飲み合わせ(健康食品・サプリメントも含む)も確認を行っています。

2)抗がん剤指導(ケモ指導)
内服薬の抗がん剤を中心に説明を行っています。初回指導時には、それまでの薬物療法や既往歴、副作用歴、アレルギー歴などを確認し、今後、起こりやすい副作用をチェックするとともに、服用中のお薬や健康食品・サプリメントとの相互作用を確認します。抗がん剤の開始後は継続的に患者さんと面談し、副作用が起こっていないか?をチェックするとともに、その時々に応じで今後予想される副作用やその軽減方法等をお伝えして、医師と連携しながら、よりよい薬物療法を目指しています。抗がん剤を服用中の患者さんで薬剤師外来をご希望の場合は、医師にご相談下さい。

7.外来化学療法センターでの薬剤指導
点滴の抗がん剤を中心に外来患者さんに説明を行っています。点滴の抗がん剤は内服の抗がん剤とは異なる副作用が起こることもあり、症状や患者さんから直接お話しを伺いながら確認をしています。副作用の軽減・予防方法をお伝えするとともに、医師や看護師、管理栄養士と連携して患者さんが通院しながら点滴抗がん剤を受けられるように支援しています。またお薬手帳に点滴抗がん剤の薬品名や特に注意する副作用をメモしたシール紙を貼付(交付)し、他の医療施設(病院や薬局)に情報を伝達しています。

8.製剤業務

市販されていない薬剤で治療上不可欠な薬剤の製剤や軟膏剤の煉合せを行っています。また、医療スタッフがより適時適切に使用できるよう薬剤の分注等も行っています。製剤の種類によっては、 院内の審査委員会で審議、承認を経て調製を行っています。
9.治療薬物モニタリング(TDM)業務
治療効果や安全性の確保を目的に、主に抗MRSA薬を中心に血液中の薬物濃度の測定結果から、最適な投与量・投与間隔を設計し、医師へ処方提案を行います。
10.麻薬管理業務
医療用麻薬は、手術中、手術後の痛み、がん性疼痛などの症状緩和に不可欠な医薬品ですが、法令により厳密に規制されています。薬剤部では手術室を含む全ての院内の医療用麻薬の適正な管理を行っています。
11.各チーム医療への参画
栄養サポートチーム(NST)、感染管理チーム(ICT)、抗菌薬適正使用支援チーム(AST)、緩和ケアチーム、リエゾン・認知症ケアチーム、糖尿病チーム、褥瘡対策チーム、禁煙チーム、改善活動チーム、小児アレルギーチームの一員として様々な場面で活躍しています。
スタッフ紹介
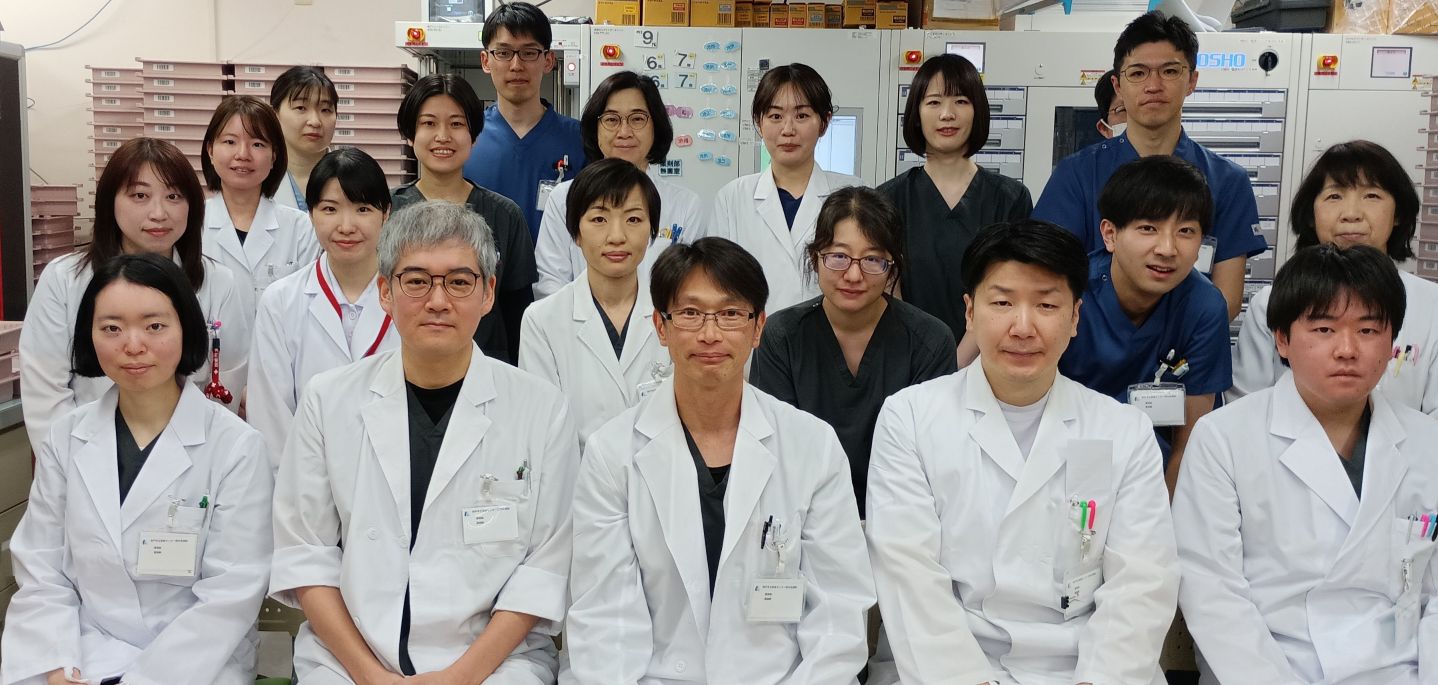
常勤薬剤師23名、非常勤薬剤師2名、薬剤師レジデント2名に加え、薬剤業務補助員6名で構成されています。(2025年4月現在)
| 薬剤長 | 平畠 正樹 |
|---|---|
| 副部長 | 中浴 伸二 |
| 副薬剤長 | 福嶋 浩一 |
教育・研修・レジデント制度
1.新入職員教育
2.薬剤師レジデント制度
高度医療、地域に根差した医療、患者に寄り添う医療など、幅広い臨床業務を実践できる薬剤師を養成することを目的に、2014年度より薬剤師レジデントを採用しています。研修期間は2年間であり、日本医療薬学会研修ガイドラインに準拠した研修カリキュラムを用いた指導を行っています。病棟業務では、レジデント在籍中に全ての病棟(8病棟)で研修します。また、毎週行われる症例検討会に参加・発表を行うとともに、1年目では、ジェネラリストとしての知識を向上させます。2年目では、NSTや、緩和医療、リエゾンでの各チーム医療、及び医療安全など、チーム医療の中での実践能力を高めます。さらに各学会の専門・認定薬剤師から各分野を学び知識を深めます。日本病院薬剤師会近畿学術大会や日本医療薬学会、日本薬剤師レジデントフォーラムで発表を行い、研究能力を高め、症例に対する探求心と臨床家としての資質を向上させます。また2年目には病院間交流レジデント研修を実施し、神戸市立医療センター中央市民病院での2~3週間の研修も行います。

3.学生実習の受入れ
臨床で必要な実務レベルの知識・考え方・スキルを身につけられるよう、また、全人的医療(身体面、心理面、社会面、倫理面)を理解してもらえるように指導を行っています。注射薬の混注業務では、実際の抗がん剤のミキシングやワクチンの分注の練習を行っています。毎週行う振り返りではただ単に机上で考えるだけでなく、臨床で感じたことを言語化し、学生同士でディスカッションすることで医療人としての気質を高めています。また、11週間の実習の最後には学生が自分で学んだことを発表し、プレゼンテーション能力を高めています。尚、発表内容によっては、各大学と共同して学会発表をすることもあります。


4.地域薬学ケア専門薬剤師研修
専門医療機関連携薬局の専門薬剤師の育成のため、保険薬局の薬剤師が週に1回、臨床の症例を通した研修を実施しています。
5.論文、学会発表、講演会など
〈論文発表〉
- Mai Ikemura, Masaki Hirabatake, Megumi Aburaya, Hiroaki Ikesue, Hisateru Yasui, Nobuyuki Muroi, Tohru Hashida : Effect of Diabetes on Outcomes in Patients With Incurable/Unresectable and Advanced/Recurrent Colorectal Cancer Receiving mFOLFOX6. Cancer Diagn Progn. 5:42-48, 2025, DOI:10.21873/cdp.10410
- Eiseki Usami, Akihiro Moriya, Taiga Jimichi, Hiroki Asano, Masayuki Miyazaki, Masaki Hirabatake, Nobuyuki Muroi, Yuki Tonogai, Yoko Hibi, Michio Kimura : Efficiently Reducing Medical Costs through Drug Vial Optimization and Multidose Vials for the Utilization of Cancer Drug Compounding Robots. Drugs Ther Perspect 41, 75-85, 2025, DOI : 10.1007/s40267-025-01140-w
〈学会報告〉
- 宇都 早希,嶋本 藍,山内 円,中浴 伸二,平畠 正樹:後期高齢者を対象としたバンコマイシンのAUCガイド導入前後の腎障害発現率と早期治療域達成率の評価.第34回日本医療薬学会年会,千葉,2024.11.2-4
- 住吉 佑介,福嶋 浩一,富山 正也,田村 昌三,野村 洋道,中浴 伸二,平畠 正樹:がん化学療法レジメン管理システムCROSSY
への検査値チェック機能搭載による業務効率化に関する検討.第46回日本病院薬剤師会近畿学術大会,神戸,2025.1.25-26
- 光武 瑞穂,渡邊 賢,野村 洋道,片岡 美咲,福嶋 浩一,中浴 伸二,平畠 正樹:ゾルベツキシマブ + mFOLFOX6 療法で遅発期の悪心を認めた1 症例.第46回日本病院薬剤師会近畿学術大会,神戸,2025.1.25-26
- 川島 佳恵,福嶋 浩一,新免 紗也,奥吉 博之,野村 洋道,中浴 伸二,平畠 正樹:薬薬連携における病院薬剤師業務の現状と課題について.第46回日本病院薬剤師会近畿学術大会,神戸,2025.1.25-26
- 森本 めぐみ,中浴 伸二,平畠 正樹:妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師への相談内容調査.第46回日本病院薬剤師会近畿学術大会,神戸,2025.1.25-26
- 三森 美佳,平野 美優,中尾 宥介,森本 めぐみ,中浴 伸二,平畠 正樹:2024年度診療報酬改定による当院の薬剤総合評価調整加算算定状況とポリファーマシー対策.第14回日本薬剤師レジデントフォーラム,三重,2025.3.1
〈講演会〉
- 平野 美優:「チャンピックス欠品をどうのりきるか」,第38回兵庫県薬剤師会 禁煙指導認定薬剤師講習会,2024.12.08
- 平畠 正樹:病院薬剤師に関する講演「病院薬剤師の業務について」,兵庫医科大学薬学部,2025.1.31
専門・認定薬剤師
| 日本医療薬学会 | がん指導薬剤師 | 1名 |
|---|---|---|
| がん専門薬剤師 | 1名 | |
| 医療薬学指導薬剤師 | 1名 | |
| 医療薬学専門薬剤師 | 1名 | |
| 日本病院薬剤師会 | 感染制御認定薬剤師 | 1名 |
| 妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師 | 1名 | |
| 病院薬学認定薬剤師 | 10名 | |
| 日本臨床腫瘍薬学会 | 外来がん治療専門薬剤師 | 3名 |
| 糖尿病療養指導士認定機構 | 糖尿病療養指導士 | 3名 |
| 日本循環器学会 | 心不全療養指導士 | 2名 |
| 日本化学療法学会 | 抗菌化学療法認定薬剤師 | 2名 |
| 日本臨床救急医学会 | 救急認定薬剤師 | 1名 |
| 日本臨床栄養代謝学会 | 臨床栄養代謝専門療養士(摂食嚥下専門療養士) |
1名 |
| NST専門療法士 | 4名 | |
| 日本医療情報学会 | 医療情報技師 | 1名 |
| 日本禁煙学会 | 禁煙認定指導者 | 1名 |
| 日本薬剤師研修センター | 研修認定薬剤師 | 1名 |
| 薬学教育協議会 | 認定実務実習指導薬剤師 | 2名 |
|
日本アレルギー疾患療養指導士認定機構 |
アレルギー疾患療養指導士 | 1名 |
| 日本医療経営実践協会 | 医療経営士3級 | 1名 |
| 兵庫県喘息死ゼロ作戦 | 認定吸入インストラクター | 1名 |
|
兵庫県 |
兵庫県肝炎医療コーディネーター | 1名 |
施設認定
日本医療薬学会
- 医療薬学専門薬剤師研修施設
- がん専門薬剤師研修認定施設
- 薬物療法専門薬剤師研修認定施設
- 地域薬学ケア専門薬剤師研修施設(基幹施設)
日本臨床腫瘍薬学会
- がん診療病院連携研修病院
地域連携の強化
神戸市薬剤師会および地域の薬局薬剤師と連携を行うことで、地域住民に対する薬学的管理および薬物療法の支援が達成できると考えます。取り組みとして、平成18年より西市民病院オープンカンファレンスを年2回開催、また平成22年より月1回の「薬薬連携検討委員会」を開催しています。また兵庫県喘息死ゼロ作戦への取り組みなどの活動を行っています。
保険薬局へのご案内
当院への疑義照会に関する取り決めについて
以前から処方の変更や一部内容修正に関する疑義照会の後、様々な要因で処方修正することができずに同じ処方を発行し、薬局さまが同じ照会をするという問題点が見られ、大変ご迷惑をおかけしています。
これらの問題点を解消するため、当院において次のような運用を実施させていただきます。
- 調剤薬局は処方内容を医師に疑義照会した後、患者へ処方薬の交付。そののち、処方変更などがあれば「処方せん内容疑義照会連絡票」に必要事項を記入し、当院にFAX送信する。
- 「処方せん内容疑義照会連絡票」に基づき薬歴を修正。

調剤薬局からの疑義照会は「処方せん内容疑義照会連絡票」を用いて、FAX送信をしていただくようお願いいたします。
※後発医薬品どおしの変更の場合、報告書は不要です。
FAX番号:(078)576-5405
「処方せん内容疑義照会連絡票(FAX用紙)(PDF:160KB)」のダウンロード
「処方せん内容疑義照会連絡票(FAX用紙)(Excel:84KB)」のダウンロード
※所定の様式で送信されなかった場合 対応が遅れたり対応困難になる可能性がありますのでご注意ください
-
ご不明な点がございましたら、当院薬剤部までお問い合わせください。
TEL:(078)576-5251(代表)
院外処方箋における問い合わせ簡素化プロトコールについて
当院では、院外処方箋における問い合わせ簡素化プロトコールの運用を行っております。本プロトコールの運用に参加をご希望される場合は、プロトコールについてのご説明をさせていただきますので、当院薬剤部までご連絡をお願いいたします。
連絡先:(078)576-5251(代表)
服薬情報提供書(トレーシングレポート)の運用について
保険薬局において、即時性は低いものの「処方医師への情報提供が望ましい」と判断された内容について、服薬情報提供書(トレーシングレポート)記入の上、FAXにて当院薬剤部まで送信してください。尚、服薬情報提供書は4種類あります。①通常の服薬情報提供書(トレーシングレポート) ※ケモ・残薬報告以外、②化学療法専用トレーシングレポート、③残薬に関する服薬状況提供書、④服薬情報提供書(兼 心不全フォローアップシート)になります。ご利用をよろしくお願いいたします。
服薬情報提供書用FAX:078-576-5405
「服薬情報提供書(トレーシングレポート)」(Excel版)(Excel:13KB)
「服薬情報提供書(トレーシングレポート)化学療法専用」のダウンロード
「服薬情報提供書(トレーシングレポート)化学療法専用」(Excel版)(Excel:14KB)
「残薬に関する服薬状況提供書」(Excel版)(Excel:15KB)
「服薬情報提供書(兼 心不全フォローアップシート)」のダウンロード
「服薬情報提供書(兼 心不全フォローアップシート)」(Excel版)(Excel:17KB)
※所定の様式で送信されなかった場合 対応が遅れたり対応困難になる可能性がありますのでご注意ください
-
ご不明な点がございましたら、当院薬剤部までお問い合わせください。
TEL:(078)576-5251(代表)
なお、従来通り疑義照会については「処方せん内容疑義照会連絡票」を用いて、FAX送信をしていただくようお願いいたします。
採用薬品一覧表
当院では下記の薬品を採用しています。順次追加・変更されますのでご確認ください。
2026年
2025年
25年5月採用薬品追加分(PDF:362KB)
25年4月採用薬品追加分(PDF:361KB)
25年3月採用薬品追加分(PDF:318KB)
電子版医薬品集
化学療法レジメン
化学療法レジメンについてはこちらをご覧ください。
- 診療科
- 看護部
- 薬剤部
- 臨床検査技術部
- 放射線技術部
- リハビリテーション技術部
- 臨床工学室(CE室)
- 栄養管理室
- 地域医療部
〒653-0013
神戸市長田区一番町2丁目4番地
 地図で見る Tel: 078-576-5251
地図で見る Tel: 078-576-5251
Fax:078-576-5358(代表)/ 078-579-1943(病診連携室 ※診療情報提供書送付先)
 地図で見る
地図で見る
-
病院案内
- 院長あいさつ
- 病院概要 基本理念・方針・沿革
- 患者の権利と責務、医の倫理
- フロアマップ、快適な環境づくりについて
- 包括同意について
- 医療安全の取り組み
- 交通アクセス
- 当院の特長(取り組み)
- 病院情報の公表
- 臨床データの研究利用に関するお願い
- ご寄付のお願い
- 一般社団法人National Clinical Database (NCD)の 事業への参加について
- 臨床評価指標
- 適切な意思決定に関する指針
- 医療費後払いサービス
- 院内フリーWi-Fi
- 厚生労働大臣が定める掲載事項
-
当院のがん診療について
-
外来のご案内
- 初めて受診される方へ
- 診療の流れ
- 診察週間予定表
- 救急診療のご案内
- 検査のご案内
- セカンドオピニオン外来のご案内
- Web予約システムのご案内
- 患者サービス向上の取り組み
- 予約制・紹介制のご案内
- 診断書・証明書について
- 治験・臨床試験について
- 病理解剖(剖検)についてのお願い
- 宗教的理由等による輸血拒否に関する当院の方針
- かかりつけ医について
-
入院のご案内
-
診療科・部門のご案内
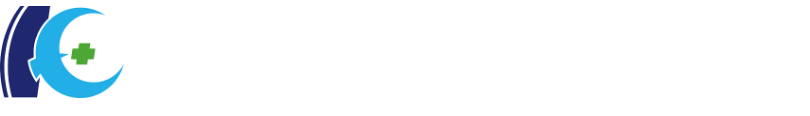




 救命救急外来の受付は24時間行っています。
救命救急外来の受付は24時間行っています。
